不文律分析
研究開発部門の沈滞した風土を変えようという意気込みを持つ人は多い。しかし、いくら動いても、さっぱり変化の兆しが無く、挫折してしまうことが多い。
その原因の1つが、方法論の欠如だ。
例えば、「悪い文化を変えよう!」というスローガンを掲げて、変化が起きるだろうか。悪い点を徹底的に調べ上げ、包括的なリストを作成したところで、変革が始まるとは思えない。もともと、自分達が抱える問題や悪い点に気付かない研究者・エンジニアは稀だ。あらためて、問題を整理しても、見易くはなるものの、処方箋は書けまい。
「風土」で文化を語るのは、文化人類学的な発想だ。例えば、人里離れた地域での特殊な文化を整理し記述するには優れた方法である。目的からいっても、そうした文化を固定するのに役立つ手法といえよう。ということは、この逆である、「変革」を目指す場合には、役に立たない可能性が高い。
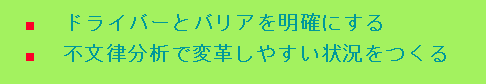
そこで登場したのが不文律分析だ。これは風土論ではない。文化を生み出す土壌の本質を見極め、どうしたら改革できるかが分る手法なのである。
変革を実現するためには、「悪い文化」をつき動かせる原動力と、その動きを押し留めようとする様々な桎梏、の2つを明確にすることが不可欠だ。これがないと、「悪い文化」の表層面をあげつらい、「ここを直そう」という網羅的な対処を進めることになる。こうした動きは、経験論で、ほとんど成果に結びつかないことが知られている。悪いことは知っていても動けないのだ。何故動かないかを理解せずに、「皆で変革の動きを進めよう!」と大声を上げても、効果は期待できまい。なかには、トップの強い意志があれば変革可能と言う人もいる。しかし、その程度で変革できるなら、とうの昔に解決している筈ではないのか。従って、不文律分析で、皆の動きを規定するルールを明確にすることは変革の出発点なのだ。
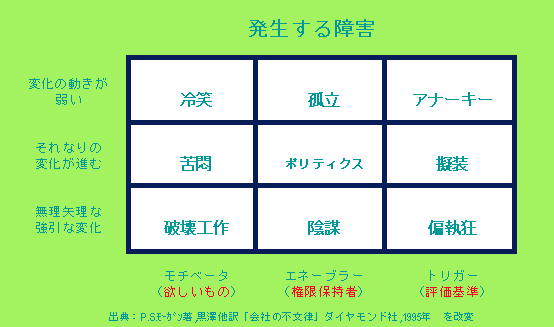
不文律分析のモジュールは、右図にある「モチベータ」、「エネーブラー」、「トリガー」からなっている。皆が、どのような形でこれら3者を見ているかを分析するのである。
ここで注意すべきは、これはルールであって、良し悪しを議論するためのものではないことだ。問題が発生しているとしたら、どのルールが原因かを調べ上げるのだ。ルールであるから、上手く運用すればプラスにも働くが、まずければマイナスに働く。マイナスを減らすためにどのように「モチベーター」、「エネーブラー」、「トリガー」を調整するかが、処方箋作成という訳だ。
この時に注意すべきなのが、変革開始による反撥である。作用には必ず反作用が起きる。反作用によって、どのような障害が起きそうか予想しておくことが、実践上、成功の決め手となることも多い。
右図は、「モチベータ」、「エネーブラー」、「トリガー」をいじると、人々がどのような態度で臨むか、類型化したものだ。小さな動きなら、「頑張っているね」と皮肉を言う位ですむが、本格的な動きが始まると、「勝手にやれよ、皆がなにをやろうと、俺は我が道を行くだけさ」と言う人が必ず登場する。不文律分析をしていれば、こうした予測を前提にして変革を進めるので、成功の確率が増すのである。
《参考文献》
Peter Scott-Morgan: "The Unwritten Rules of the Game; Master them, shatter them, and break through the barriers to organizational change"
McGraw-Hill, Inc. NY U.S.A., 1994 $21.95-
・著者は英国人、研究者から経営コンサルタントに転身
・翻訳書(ダイヤモンド社刊)もあるが、付録の実例が役に立つので原典がお勧め
(但し、映画や文学等の一般素養を欠くと読みづらい。)
・欧米の企業も不文律は深刻な問題であり、この分野に切り込んだ初の手法という評価が定着
・具体的に企業を変える糸口発見の方法論をわかりやすく解説
(C) 1999-2000 RandDManagement.com


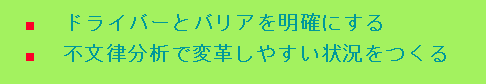 そこで登場したのが不文律分析だ。これは風土論ではない。文化を生み出す土壌の本質を見極め、どうしたら改革できるかが分る手法なのである。
そこで登場したのが不文律分析だ。これは風土論ではない。文化を生み出す土壌の本質を見極め、どうしたら改革できるかが分る手法なのである。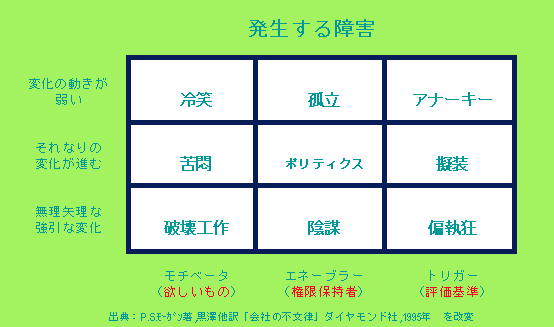 不文律分析のモジュールは、右図にある「モチベータ」、「エネーブラー」、「トリガー」からなっている。皆が、どのような形でこれら3者を見ているかを分析するのである。
不文律分析のモジュールは、右図にある「モチベータ」、「エネーブラー」、「トリガー」からなっている。皆が、どのような形でこれら3者を見ているかを分析するのである。