↑ トップ頁へ
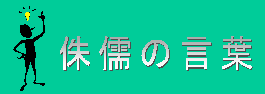
2000.6.19
|
↑ トップ頁へ |
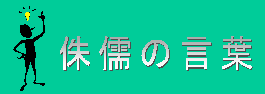
2000.6.19 |
|
|
|
化学物質安全性研究の絞り込み…化学物質の安全性問題の議論は尽きない。当事者たる化学物質メーカーの報告を信頼しないのが一般的風潮だが、メーカーが自ら対処策を考えない限りこうした問題は解決し得ないだろう。どのように検討対象物質を絞り、どんな観点で安全性を考えればよいのかを決め、この課題に取り組まない限り、問題が次々と列挙されるだけになる。問題を絞り込み、解決策が打ち出せる安全性研究が必要ではないだろうか。 例えば、「内分泌系に作用する化学物質に関する調査報告」(日本化学工業協会1997年)では100以上の物質について検討を行っている。これだけでも、大変な仕事である。しかし、歴史の教訓からいえば、気付いていない危険物質や抜け落ちはありえる。この数でよいという保証はない。といって、無原則に検討対象物質の数を増やすことに意味があるともいえまい。そうなると、重要なのは、どのように検討対象を絞り込むかを考えることではなかろうか。 化学物質の種類ははとてつもない数である。ケミカル・アブストラクトのデータを見ると年率1桁の高い方で新規物質が増えている。今までなら、年間増加は百数十万個という見方でよかったが、コンピュータの発達で、ロボット合成と自動分析が急速に進みつつあるから、今後は複利で増える可能性が高い。21世紀の早い段階で、2000万個の化学物質がデータベースに揃うようになるのではないか。とてつもない数になる。 といっても、ケミアブは科学段階の話しだ。ある程度の量で、商業的に利用される物質の数は、かなり小さい。しかし、それでも、欧州の化学業界では、10万種程度をリストアップする。 日本では、化審法対象物質は1999年段階で2万4千近くまで増えてきたが、このままの伸びなら3万程度であろう。 これだけ多数の科学物質のなかから、危険物質を検討しなければならないのだ。明確な方法論や論理は不可欠といえよう。この場合、2つの問題がある。 ひとつは、「化審法の対象外の物質も要検討なのか?」、という疑問。 もう一つは、化審法の視点では安全性判定ができなくなっている可能性だ。 緊要なのは、後者の問題だ。 化審法における「安全性」の考え方は明確である。簡単に言えば、3点に集約される。 ・まずは、難分解性のものは問題が大きい物質と考える。 ・次ぎに、生体に蓄積するものは危険と見る。 ・その上で、慢性毒性があるものを避ける。 重金属、特定の有機金属、PCB・DDT等の有害物質の問題への対応はこうした化審法の観点で十分と思われる。不幸なことではあるが、被害の程度を示すデータが揃っていて、危険性は評価できる。危険物質は即刻製造禁止として、発生源を絶ち、貯蔵品処分や使用品の無害化へと進むだけだ。基本的な道筋は明確だ。 この場合、製造企業を批判することに力を注ぐより、技術的に一番経験がある企業に無害処理化のインセンティブを与える方策を考案する方が有意義と思う。すでに使用された有害物質の回収は難しいだろうが(国内使用量はPCBで6万トン、DDTが16万トン程度と聞く。)、できる限り対処するしかなかろう。 ここでの緊急課題は、すでに危険であることが判明している物質(例えばダイオキシン)の発生源を絶つ手立てが遅れている場合だ。これは、政治の問題だ。 有害物質の類似構造品や代替可能製品についてのチェック体制を構築すれば、大きな問題は残っていないといえよう。 ところが、このような方針では対応できない恐れが出てきた。生殖毒の研究が進んできたためだ。 化審法の慢性毒性は、基本的には被曝1代の判定といえる。将来世代に影響が出る可能性が指摘されても、この判定では黒白を語ることは不可能だ。 特に困難性が増しているのは、ppbやpptといった極く微量で影響が出る「環境ホルモン」の存在が確認されたからだ。「環境ホルモン」問題の難しさは、どのように毒性試験をすべきかさえ明確にできない点にある。しかも、どこの家庭にもある汎用樹脂製品の原料であるビスフェノールA、スチレン・モノマー、樹脂に添加される可塑剤のフタル酸エステルといった物質が対象なのだ。 このような物質は明らかにホルモンの構造とは異なる。にもかかわらず、ホルモン受容体と反応するという。今までの理論では、特定構造の物質しか受容体の鍵穴に入らない筈だ。本当だとしたら、今までの科学では解明できない作用が発見されたといえよう。 すでに指摘されている「環境ホルモン」物質の危険性を細かく調べたり、新たな該当物質を探すのも大切かもしれないが、この作用の解明を急ぐ必要があるのではないか。作用が分らなければ、一体どのような物質が問題なのかもわからない。やみくもに、10万個もの物質を検討することなど現実的とは思えない。基礎理論構築を急ぐ必要があるのではないか。 もしも、ホルモンの作用が極めて重篤な影響を与えるとするなら、「環境ホルモン」だけを検討するだけでは決定的に不足と言わざるを得まい。本来のホルモン物質も拡散しているからだ。ホルモン物質は極く微量で作用するから、すでに影響が出始めている可能性も否定できない。食べ物や飲料水から摂取するホルモン量など検討したこともあるまい。例えば、以下の疑問がすぐに湧く。 ・農業で使われているホルモン系の物質が農産物を通して体内に入る可能性や影響は? ・飼料としてホルモン様のものが与えられて育った家畜等を食した場合の影響は? ・避妊薬をはじめとするホルモン系医薬品が海水に流出していると考えられるが、海産物を食すると影響はあるのか? ・もともと植物に含まれているホルモン類似成分は問題ないのか? こうした指摘を始めると、きりがない。ホルモンが将来世代に影響を与えるのか否かの解明がなければ、不安をつのらせる意見はいくらでも出てくるだろう。 ホルモン摂取の生殖毒としての危険性の有無と、非ホルモン構造物質のホルモン類似機能発揮メカニズムの2点について、明確な見方を早く確立して欲しい。 侏儒の言葉の目次へ>>> トップ頁へ>>> |
|
|
(C) 1999-2004 RandDManagement.com |