↑ トップ頁へ
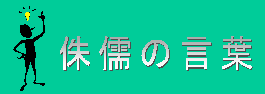
2003.7.31
|
↑ トップ頁へ |
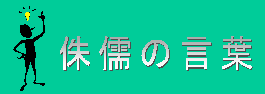
2003.7.31 |
|
|
|
動物生態学の援用…「熱帯雨林の果実食性霊長類とその餌資源:最適採食のための適応」とのタイトルを見た瞬間、産業界の人々は関心を失うかもしれない。これは、1988年の動物学・博士課程学位論文名である。 霊長類の研究では、日本のアカデミズムは世界最先端を走っていると言われている。その系譜に位置付けられる論文だが、おそらく、この分野の人しか読まない論文だろう。 ところが、実際は、こうした研究成果は部外者からも注目を浴びる。動物の生態を、ヒトの生活に当てはめるというアナロジーの面白さがある上、新鮮な視点を得られるからだ。 このため、こうした専門家のやさしく書き下ろした本が広く読まれることも多い。 例えば、「ゴリラの森の歩き方 私の出会ったコンゴの人と自然」(三谷雅純著 地人出版 1997年)との題字を見かければ、興味を引かれる人も多いだろう。 当然ながら、動物の生態よりは、コンゴの人々と、フィールドワークの実態を描いたものだ。研究成果そのものを伝えるというより、付随する話しが中心になる。 よくある話しである。 しかし、なんといっても一番注目されるのは、比較生態学への拡張だろう。動物との共通点を考えて、ヒトの生態の特徴を明確化する訳だ。 この影響力は強いようで、子育てや教育の分野での議論でも、動物の生態が援用されることが多い。 ゴリラや日本サル社会のルールをヒトに当てはめる主張は、論理的根拠が不鮮明だが、議論を深めるのに役立つのは間違いないようだ。 といっても、動物生態学者が、幼児教育の分野に入ることは稀だ。 ところが、環境倫理学には親和性があるようで、多くの学者が参加してくる。 先の本でも、著者は、研究のために手付かずの無垢の自然に進入することの問題性も指摘しており、環境問題への関心が高いことがわかる。研究対象の動物の気持ちがわかると、動物から見た自然環境が気になり始めるのは極く自然な流れなのだろう。 しかも、環境倫理学は、その発想がいかにも古臭い。「人間も生物の1種だ」とか「生態系のバランスが重要」というドグマから一歩も進んでいないように見える。 斬新なセンスで研究を進めてきた、気鋭の動物生態学者が、新しい学問体系をつくりたくなるのも当然かもしれない。 ・・・という話しをしていると、好事家の学問の話題と思われがちだ。 実は、このような、ビジネスに縁遠く見えるアカデミズム分野の普通の人達に、ビジネス分野には興味が無いのか、それとなく聞いてもらった。残念ながら、応えは曖昧だった。興味以前だったようである。 残念なことだ。 ビジネス分野から眺めると、眼光鋭い動物生態学者の頭脳は魅力的である。 普通の人にはとても耐え難い長時間の観察を続け、収集した膨大なデータから、動物の一寸した行動に、新しい意味を発見する。このような学者の姿を、商品企画担当やマーケッターは、羨望の眼差しで眺めているのだ。 対象は全く違うが、本質を探る苦闘は同じだと思う。(但し、観察の忍耐力の差はとてつもなく大きい。) 顧客が、本当のところ、一体何を望んでいるかは、表面的なアンケートやインタビューではほとんどわからない。潜在ニーズ探索といっても、現実には、五里霧中の検討、が実情なのだ。現実の生態を眺めて、ニーズを想像するしかないのである。これがことのほか難しいのである。 多くの場合、お客様が、店頭で、何故当社の製品でなく、競合製品を選ぶのかさえ、はっきりしていない。 顧客は誰だかはっきりわかっている。しかし、その「生態」はほとんど理解できないのだ。 商品化力は十二分にあるにもかかわらず、ニーズが分からないため、皆、苦労しているのである。 動物生態学者が、ヒトの生態に関心を持ってくれたら、道は開けるのではないか、とビジネスマンは密かに期待しているのである。 しかも、日本の動物生態学レベルは世界最高水準なのだ。 侏儒の言葉の目次へ>>> トップ頁へ>>> |
|
|
(C) 1999-2004 RandDManagement.com |