↑ トップ頁へ
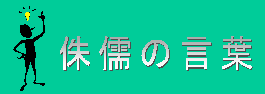
2010.10.18
|
↑ トップ頁へ |
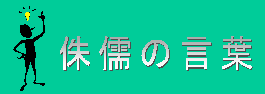
2010.10.18 |
|
|
|
民事再生法適用出版社を眺めて…〜 理論社とは、流行本出版社を目指して脱皮を図っていた会社なのでは。 〜よりによって、国民読書年だというのに、有名出版社が民事再生法の適用を申請。理論社である。 なつかしき絵本の出版社ということで情緒的なコメントが散見される。確かに昔はそうだったが。 新聞記事のタイトルもたいていは児童書の出版社とされているが、小生のイメージは全く違う。児童が減るからか、ヤングアダルト層(古典的な言葉ではティーンエージャー)へと手を広げることに精力を注いでいる出版社という感じしかしない。 こんなことをするようでは、どうにもならないと見ていたが、予感的中といったところ。と言っても、実はそんな本を一冊もよんだことはない。ただ、次のようなシリーズ企画はマスコミ報道があったから、耳にしているといった程度。ただ、御蔭で、ここで本を出しまくっている出版社との印象が強く残っているのである。 ・YA新書 「よりみちパン!セ」 ・「星新一YAセレクション」 ・「理論社ミステリーYA!」 ・「理論社YA翻訳シリーズ」 (おそらく、“YA“としたのは、アダルトの語感を嫌ったのだろう。) ちなみに、新書の著者とは西原理恵子、叶恭子、辛酸なめ子、中村うさぎ、貧困の湯浅誠、童貞映画監督の松江哲明、養老孟司、しりあがり寿、みうらじゅん、・・・とくる。まあどこの児童出版社がこのような人達を起用するというのか。 この手の商売は、書店の棚取り合戦とマスコミ受けしそうな宣伝で勝負がきまる。下手な鉄砲なにやら方式。作家も本も使い捨て。良書作りを称している出版社がなにが面白くて、こんな商売をしているのか外部の人間にはさっぱりわからん。 ミステリーで言えば、 2010年出版の典型は“有栖川有栖: 「闇の喇叭」”か。この著者は東京創元社刊行の「学生アリス」と、講談社系刊行の「作家アリス」で有名な方だそうである。人気作家の一作を加えようという訳。いかにも日本流のやり方。ジャンルが同じ本にもかかわらず、作家が出版社を一本に絞らないのだから、どこでもよいということ。日本の出版文化を誇る人がいるが、小生は、この状態で質が高くなる筈などありえないと思うが。こればかりは、日本の風習であり、作家の体質の問題だからどうにもならないが。 〜 大手の児童書出版社はどうみても業態が異なる。 〜 それはともかく、小生のような素人から見れば、児童書の大手出版社は特殊な業態である。商品の話ではなく、売り方。他の出版社と違い、図書館御用達企業に映るからだ。課題図書指定にでもなれば、自動的に大ヒットの世界としか思えない。狭い社会で生活する人達に良質とみなされる本さえ作っていれば確実に売れる仕組みができあがっていたのではないか。 そういっても感覚が伝わらないかも。わかり易い例をあげれば、千葉茂樹訳 和田誠挿絵: 「オ−・ヘンリ− ショ−トスト−リ−セレクション」(全8巻)。もちろん、小学校高学年〜中学生向の企画だ。全巻揃えれば、1万円の出費となり、親が買い与える金額としても過大。どう考えても、基本は図書館蔵書。もちろん、本邦初翻訳もあり、大人でも欲しいかも知れないが、この価格ではというところ。 そんなビジネスをしている企業が、リスクが高いティーンズ相手の市場に進出したのだから驚き。当然ながら、失敗を前提に、事業が不調なら、屋台骨を揺るがす前に即撤退すべきなのは当たり前の話である。実に無責任な経営と言わざるを得まい。 おそらく、YA分野で、返本スピードを超える納本スピードを実現して、実需でない売上増をはかって資金繰りで生き延びてきたのだろう。そのうち、大当たりする本もあるかも、というギャンブルにかけていた訳である。 この分野を率先して開拓したとの自負もあろうが、社会に対する責任感の欠如以外のなにものでもなかろう。 もともと、YA市場は不安定。児童ならお金は親から流れるし、成人には自分で稼いだお金があるが、その狭間は金銭的には潤沢な訳ではないからだ。ただ、多感であり、流行に流され易い年代であるから、読書が重要であるのは明らか。だが、この層が喜んでとびつくのは、多分、日本的なライトノベルと漫画。しかし、それも一過性かも。様々なエンタテインメントがこれでもかと飛び込んでくるのが実情なのだから。 しかも、YA市場というが、日本の場合は、出版社+図書館+教育現場が作り上げた幻想でしかないかも。本屋の棚割りに、YAなど無いからだ。書店面積は限られており、有象無象の出版物が溢れかえるなかで、ジャンルが無いのは致命的では。たとえ、YAのベストセラーが生まれたところで、ジャンルが確立されていないのだから、YA市場全体の底上げには繋がるまい。 図書館相手のYA良書の看板では、大手出版社の業容が保てるとは思えないのである。 〜 産業界の沈没で経営的に傾いてしまった出版社もある。 〜 この話とは全く異なるのが、工業調査会。2010年8月末日に事業停止。 名称は出版会社らしくはないが、研究開発の話題を中心とする雑誌と本をだしてきた企業である。 「電子材料」、「プラスチックス」、「機械と工具」、「化学装置 」といった産業の裏方的な部品や材料という地味な分野が主体。ただ、日本の半導体産業が一瞬輝いた時代に、一躍有力出版社に変身。「インターネプコン・ジャパン」と言えばわかる人も多かろう。 編集長の才覚が大きかったのだが、日本の産業界を支えるという出版社の意気込みが成長の原動力になったと言えよう。 しかし、ついに息の根が止まってしまった。まあ、一般書的な分野に手を広げすぎたこともあるが、本質的には、日本の産業界にこのような出版社を支える力はもうないということ。顧客の状況を考えれば、売上が最盛期の3分の1程度に陥ってもおかしくないのでは。 なにせ、雑誌の場合、まともな取材をすればコズト割れ。企業内情報はなんであれ出すなという状況だが、大学の先生を活用すれば、ピント外れのご自分の話になりかねない。出版社としては対処は難しいものがあろう。 書店の理工棚のこうした分野も悲惨と聞いたことがある。産業関係で売れるのは、大学で指定される本とコンピュータ関連で、そこから外れると紙焼けしていたりするという。書店経営からすれば、返本して資金繰りに当てたいのが実情なのかも。 言うまでもないが、この分野こそ日本の“モノつくり”の原点である。ここではヒトは簡単に育たないからだ。長期雇用で育て上げるしかなく、従業員も将来が見えるからその分野で一所懸命に学び続ける好循環ができていた。この輪が切れたのである。正確に言えば、切れたのではなく、切ったと言うべきである。従って、当面は、残っている人達の慣性力でなんとかなるが、早晩、弱体化は逃れられない。 この強みを最終製品にどう生かすかのスキルで商品力に差が生まれるのだが、大元はないがしろにしておいて、“すり合わせ技術で優位に立とう”といった曖昧模糊としたスローガンですます企業が多い。これでは、没落の流れは止まるどころか、加速されること必定。 そんな動きが、先ずは出版界に影響を与えたということ。 --- 帝国データバンクの倒産[再生法適用]情報 --- http://www.tdb.co.jp/tosan/syosai/3358.html http://www.tdb.co.jp/tosan/syosai/3335.html 侏儒の言葉の目次へ>>> トップ頁へ>>> |
|
|
(C) 1999-2010 RandDManagement.com |