↑ トップ頁へ
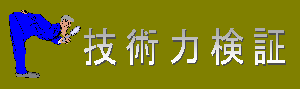
2000.1
|
↑ トップ頁へ |
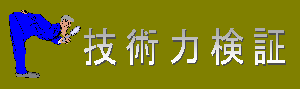
2000.1 |
|
|
|
情報通信分野のR&D失敗の理由…90年代、情報通信分野では、欧米国企業が市場を席巻した。一部の製品領域を除けば、日本企業の出番は限定的だった。情報通信技術で日本企業は出遅れたと言えよう。ところが、80年代、日本企業の技術マネジメント力の評価は極めて高かったのである。時代を読み切り、的確な技術領域に資源を集中投入し、ダイナミックな研究開発をすると見られていた。実際、世界に先駆け、「情報処理技術と通信技術が融合し、その2つを取り持つのが半導体だ。」と喝破したのは日本企業だ。技術の流れを明確に示した優れたメッセージだった。そのため、日本企業が今後リーダーとして飛躍するとの予想が広がった。 しかし、現実は全く逆である。 どうしてこうも急速に技術競争力を失ったのか。(もともと弱体と見る人もいるが。) 複雑な要因が絡み合うが、単純化すると、5点に絞られよう。(コンペテイティブ・インテリジェンス、キラー・アプリケーション、世界標準、受動的態度、半導体設計技術) (主要因・その1) コンペテイティブ・インテリジェンスの方法がわからなかった。---IBMやベル研を注視していれば、技術の波が読めたのはせいぜい70年代迄だ。80年代後半からは大学・研究機関やベンチャーを中心とするセンター・オブ・エクセレンスの動きが重要になった。ところが、重要な動きと気付いても、今までの情報収集方法で対応してしまった。最初は、どこから情報を集めるべきかも分らないし、沢山情報を集めてもフィルターにかけるノウハウも無かった。その上、海のものとも山のものとも分らぬ新技術の重要性評価能力にも欠けていた。こうした能力不足をすぐに補うのは難しい。 (主要因・その2) キラー・アプリケーションを創出できなかった。 (その2A) 色々チャンスはあったが、独自で魅力的なソフトを作ろうとはしなかった。---80年代に、「一太郎」というキラー・アプリケーションがPC-9800発展の原動力になった。これ以後、国内で目立つ製品は無い。ソフト開発のキャパシティが小さいので、欧米に比べればハンディキャップも大きい。一方、海外では次々と魅力的な応用が登場した。日本では、これらの日本語化や、時間をかけた類似ソフト作成が、開発の仕事になってしまった。 (その2B) カスタムメイドや独自規格のアプリケーションにこだわった。---汎用製品開発を避け、自分の顧客ベースの維持を優先した開発を進めた。そのため、開発費用が嵩んでしまった。ところが、顧客は限られており、回収しにくい。悪循環が産まれた。 (その2C) 「モノ作り」よりは、モノのコンセプト創造が重要になった。---作り方の特許やノウハウでは、バーゲニング・パワーが発揮できなくなった。 (主要因・その3) 世界標準に合わない製品が駆逐されることへの対応が遅れた。 (その3A) 市場主導の標準化が進んだ。---新技術の登場で標準が急速に変化したり、国際機関の規格が無視されることもある。急激な変化に対応可能な、速い意思決定と柔軟な組織を持つ企業が優位に立つ。 (その3B) 低価格・高機能商品でも、標準に合わなければ全く利用されない。---皆が使える互換性が不可欠になった。機能や品質の差よりも、標準対応かどうかが、成功を左右する要因になってしまった。しかも、その標準はグローバルに通用する必要がある。ローカル規格にこだわり孤立すると、グローバル市場に進出するには重複した研究開発が必要となり、自ら首を締めることになる。ローカルの成功がグローバルでの敗退に繋がる可能性が高い。 (その3C) 日本から世界標準として提起可能な分野が、極く一部だった。---キーコンポーネンツ、アーキテクチャー、通信プロトコル、言語、基本ソフトのほとんどの領域で、メーカーが主体的に係われなかった。MPEGだけは例外的だ。このことが、通信の本流ではなく、傍流に力を注ぐ結果になった。優位分野のパッケージ(記録メディア)や放送規格制定の方に力をいれすぎた。 (主要因・その4) ダウンサイジングの波に受動的態度をとった。 (その4A) メインフレーム関連プロジェクトが大幅に残った。---ダウンサイジングでメインフレーム事業が大きな影響を被ることを知ってはいたが、競合対策の観点を重視したため、抜本的施策を躊躇した。この分野の開発プロジェクトには、最低でも、数百人と1千億円レベルの資金投入が必要だから、この影響は極めて大きい。投入したからといって、成長する見込みはないが、競合には敗退する。従って、中途半端な動きを続けたのである。(尤も、これは日本企業に限らない。) (その4B) 鍵を握るパソコンやサーバーの国内価格を高止まりさせた。---ダウンサイジングの波に乗るためには、「モノつくり」優位のうちに大胆な低価格でハードの大量販売を先駆けるべきだったが、収益確保に走った。このため、国内市場が思った程開けなかった。一方、海外市場でも、家電製品のような疾風怒濤の展開ができずに終わった。知的所有権の問題があったので、「モノつくり」優位企業が下請け製造業者として米国企業を支えたからだ。 (その4C) 変化のスピードが速いにもかかわらず、それに合わせた動きをとらなかった。---ドッグ・イヤーと呼ばれる業界になったにも係わらず、リスク承知で新しいことに次々と挑戦していくような経営方針はとらなかった。特に、インターネットの動きに対しては、様子見で臨んだ。 (主要因・その5) 半導体設計技術が弱体だった。---80年代に日米間で半導体をめぐる軋轢があった。接触を繰り返すうちに日本の実力がわかってしまった。日本の回路設計技術は技術者の個人芸中心のカスタム志向が強く、CAD利用の方法論、設計用言語の標準化、設計プロセスのモジュール化が遅れていた。しかも、90年代を通して、この差はほとんど狭まらなかった。 その上、日本企業のメイン商品であるDRAMは、インテルのCPU技術発展シナリオに合わせた開発を強いられた。そのため、技術の波はコントロールされてしまい、DRAMは半導体技術開発の牽引車としての役割を失った。 この弱みは、さらなる問題を引き起こす。80年代に「モノつくり」で優位性を築いたにもかかわらず、設計力が弱かったために、設計と製造の相互関連のノウハウ蓄積ができなかった。その結果、製造技術の鍵は、検査検品システム、精密製造機器、製造環境設定に移ってしまったのである。半導体メーカーはニーズを明確にする役割が中心になり、外部の機器・装置メーカーの研究開発の方が重要になってしまった。半導体メーカーは独自の製造技術体系を喪失したとも言える。当然、後発企業にとっては躍進のチャンスである。こうして、日本企業はポジションを失ったのである。 さて、これらの問題があるとしたら、21世紀にむけて、解決する方向で動いているといえるだろうか。 なかでも重要なのは、半導体分野の競争力回復である。携帯電話では、もともと強い機能部品に加え、ASICや高速処理ICでも一歩先を進んでいることを示した。これが、システムLSI化の流れに乗った動きなら、競争力回復もありうる。この分野はこれからの日本の産業を牽引する戦略分野だ。集中的な資源投入と的確な研究開発戦略で、競争力の早期回復を図って欲しい。 技術力検証の目次へ>>> トップ頁へ>>> |
|
|
(C) 1999-2004 RandDManagement.com |