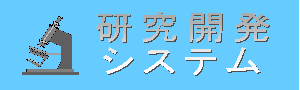
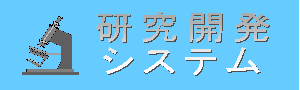
パーソナル用品事業の飛躍の種は豊富… パーソナル用品分野は、商品の良さの判定基準が不明瞭になりがちである。ここが技術屋泣かせのところだ。個人個人の好みが異なるため標準的な測定尺度を作りにくい。目標設定が極めて難しいのだ。
パーソナル用品分野は、商品の良さの判定基準が不明瞭になりがちである。ここが技術屋泣かせのところだ。個人個人の好みが異なるため標準的な測定尺度を作りにくい。目標設定が極めて難しいのだ。例えば、「体を心地よく洗える」ことを測定する基準を質問すれば、回答は千差万別となろう。答えを無理にまとめれば一般論すぎ役に立たない。美や気分に関する評価尺度は個人と社会の文化に依存するものであるから、原理的にこの困難はつきまとう。残念ながら、現在の科学はこうした領域を十分解析できるレベルに達していない。従って、この分野での研究開発の成功は、個人個人の違いを捨象したニーズを明確化できるかどうかにかかっていると言えよう。 といっても、実際の研究開発プロセスでは、ニーズ明確化とは流行りそうな商品コンセプトの創出活動に他ならない。この活動は製品試作に繋がり、さらに試作品のメリットを顧客がどのように評価するか調べフィードバックし改良につなげるというループができる訳だ。即ち、以下の3つのプロセス設計が研究開発の質を決めることになる。 1 流行りそうな商品コンセプトの核となる新機能の提案 2 新機能の訴求ポイントに合わせた商品設計 3 顧客に対して新機能利用のメリットを提起する方策 このうち、多くの企業に苦手意識があるのが1である。確かに、新機能の提案で常に優位を保つのは並大抵のことではない。しかし、個々人のミクロのニーズを理解した上で、大局観から潜在ニーズの仮説を打ちたてることや、新機能の提案自体はその分野のプロを目指す集団にとってはそう困難なことではない。ニーズが沢山ありすぎることが問題で、ニーズが分からない訳ではないからだ。この場合、重要なのは大局観である。そうなるとグローバルな視点を持つことが重要になる。個人や地域の特殊性を捨象し、ヒトの生理的要求という原点に立ち戻って考えられるからである。 個人の好みには「伝統文化」が色濃く反映しているので、日本人がグローバルに戦うのはそう簡単ではないという人もいるが、実際は逆の例が多い。自社の技術を武器にグローバルな視点で製品を開発し、世界最高の製品を作り上げ、成功を収めている企業の実例は数多い。 このような研究開発システムにおけるマネジメントで注意すべき点がある。技術重視ではあるが、常にアウトプットをパーソナル商品のコンセプトにまで高めていることだ。決して、新技術の初適用品を試売し市場の反応を見るというプロダクト・アウト型ではない。顧客の琴線に触れるような新たな「満足」のポイントを追求するべく研究開発が進められ、ニーズ仮説で設定した目標レベルが達成され始めて新製品を提案しているのである。いわば、創造的プロダクト・アウトとでも言える展開である。この場合、訴求に合致するような商品デザインと高品質製品を保証できるだけの作りこみが可能な組織構築が不可欠である。その上で、こうした組織と商品コンセプト創出者の間でスムースな連携ができるような、コミュニケーション・スキルを身につけていないと、力が発揮できないのだ。このスキルが弱体化すると、いかに革新機能であっても消費者が商品に個性を感じず魅力は乏しくなるから、単なる特殊機能品で終わるか、コモディティ化の道をたどることになる。商品のアイデンティティ確立を図れるように、社内の製品開発プロセスを設計しておくことが重要なのである。 といっても、このような創造的プロダクト・アウトを成功させるのはそう簡単なことではない。というのは、新技術に賭けた瞬間に商品開発プロジェクトが始まるからだ。この分野では、新しい要素技術を展開してみるということは、それ自体が新しい商品コンセプトを考えることに繋がる筈なのだ。そのようなセンスが無い場合は古典的なプロダクト・アウトとなる。この仕組みを図示したのが下図である。 伝統的方法と異なるのは、潜在ニーズに対応しそうな類似商品を検討することではなく、自社で考えるシナリオを優先させることだ。このため一見するとプロダクト・アウトに見える。しかし、顧客と一体化した動きをしていれば、研究開発部隊が提起するシナリオが支持され、新しい潮流が顧客から発生していくことが多い。但し、顧客と一体化した動きをコンセプト創出に限定していたのでは、成果はあがりにくい。コンセプトに合わせた試作品を作成し、代表顧客からフィードバックを受け、商品コンセプトを磨く必要がある。徹底的に磨いていくことで、極く自然に革新製品にまでレベルが高まっていくのである。従って、新潮流をつくりそうな消費者からフィードバックできる仕組みは不可欠だ。この仕組み構築は難しいことではない。ファンやマニアといったリードユーザーと一緒になって開発すれば十分なのである。イノベーションを生もうという姿勢に共感する消費者にモニターを頼むだけでいいのである。場合によっては、社内にファンやマニアを抱えていたり、開発者自身がリード消費者を兼ねてもよい。要は、潮流を作ろうという意気でまとまっている小集団を活用することである。
|