↑ トップ頁へ
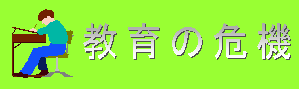
2003.2.24
|
↑ トップ頁へ |
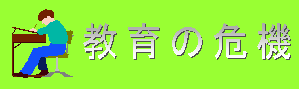
2003.2.24 |
|
|
|
学会の体質問題…日本人が3年連続でノーベル化学賞を受賞したが、田中耕一さんは日本化学会の会員でなかったという。そのため、2003年3月の同会での講演前に、急遽入会することになったそうだ。(http://www.yomiuri.co.jp/04/20030222i501.htm)驚いたことに、化学賞授賞者が日本化学会の会員ではない。・・・これこそ、日本の「学会体質」そのものといえよう。しかし、このことについて語る人は稀なので、解説しておこう。 授賞対象の「soft desorption ionisation method」の内容を知らなくても、「プロテオミクス」という用語は、ほとんどの人が知っている時代だ。その蛋白質解析の中核を担うのが、新型質量分析であることもよく知られている。 今や、素人でも、新しい質量分析手法の登場によって、蛋白質解析が急速に進歩した、位の知識を持っている。 ところが、多くの人が、この技術の発祥元が田中耕一さん、とは知らなかった。ノーベル賞受賞で始めてわかったのである。 誰も、この事実を語らなかったから当然といえる。 といっても、早い段階で、「奨励賞」(日本質量分析学会)を授賞しているから、専門家がこの事実を知らなかった訳ではない。科学への貢献を十分知りながら、権威者が、この事実をできる限り知らせないようにしたのである。(そうでないなら、真っ当な技術評価ができない似非専門家しかいないことになる。) 今回の報道ではっきりしたように、授賞するまで、学会加入の勧誘さえしなかったのである。 こうした点に関して、ジャーナリストはなにも語ろうとしない。 その一方で、面白おかしく、企業の処遇が薄すぎるという点をあげつらう。日本では、企業批判は自由だが、学会批判はタブーなのである。 これが、ジャーナリストが日本社会で「生き抜く」コツである。 しかし、ジャーナリストが指摘する「企業内処遇」の論調は度がすぎている。批判すべき「学会体質」については黙して語らず、上手くいっている企業内人事マネジメントを批判し、そのような環境を壊そうとするのである。 実務家からみれば、処遇に関して、特別批判すべき点は見当たらない。というより、技術者管理は優れていた、と考える。 実際、本人が仕事に満足しており、周囲とのチームワークも上々なのだ。 しかも、以下の、人事の鉄則を遵守している。問題などない。 ・ 人の管理を嫌う研究者・エンジニアを、ラインの管理職に登用しない。 ・ 企業への貢献が認められない無い場合は、昇進を見送る。 問題があるのは、明らかに学会である。 企業も、学会で学問的な貢献が認知されれば、企業収益に直接貢献していなくとも、相応のポストを用意するのが普通である。企業は、収益を目指すからといって、学問的貢献を全く無視する訳ではない。技術立社を目指す企業には、「フェロー」のようなポストもある。 とはいえ、学会が無視しているのに、企業が、自社の社員の成果を、「学問的な価値が極めて高い」と勝手に見なせる訳がない。学会が認知しないのに、「フェロー」レベルの処遇を行っていたなら、独善的経営の企業と見なさざるを得まい。 この点でも、企業のマネジメントは極めて健全だった。 素晴らしい成果を生み出したにもかかわらず、一介の「研究者」扱いは問題、というなら、それは企業の問題ではなく、学会の問題なのである。 日本の学会は、弟子を抱える閉鎖的集団の集まりであり、その集団に属さない研究者・エンジニアを排除する傾向がある。 田中耕一さんも、授賞は化学分野だが、「所属」分野は化学系ではなく、電気系だ。化学系の学会員から見れば、部外者だから、一緒に活動したくないのである。 当然ながら、部外者の成果はできる限り認めたくない。 学会の年会に出席すれば、こうした体質の一端を垣間見ることができる。 「素晴らしい報告で感銘を受けました。一つ、教えて頂きたいのですが、・・・」といった質問が続く。ここには、なんの緊張感もない。 本来なら、新理論や発見についての、甲論乙駁があってしかるべきだ。 ところが、最新の成果を伝える年会での講演でも、侃侃諤諤の対論など全く見かけない。 ということは、議論を呼ぶ内容が無いか、反対派を排除した、と考えざるを得まい。 これこそ、日本の学会が抱える最大の問題といえよう。 教育の危機の目次へ>>> トップ頁へ>>> |
|
|
(C) 1999-2004 RandDManagement.com |