↑ トップ頁へ
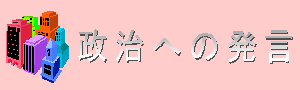
2000.5.6
|
↑ トップ頁へ |
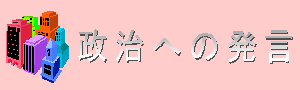
2000.5.6 |
|
|
|
公共事業型の科学振興策…90年代初頭の、産業界やオピニオン・リーダーのの見方は勇ましかった。---「日本企業は、技術革新の次の波を起こそうと全力投球しており、巨額の投資を行っている所だ」(Wall Street Journal No.28 1992 Dec.)は典型。日本企業は商用化技術を磨きあげることに注力し奏効したが、これからは基礎研究にも本格的に挑戦するとの宣言だ。「企業のみの力でイノベーション創出可能」との心情を吐露していることが注目点。明らかに、大企業外での、科学分野の研究活動振興を軽視した。70〜80年代、国内の科学研究者の力を借りなくとも、エレクトロニクス産業分野で目覚しい躍進を実現できたのだから、そう考えるのも当然だ。 ところが、90年代に、様相が一変した。 米国で、新技術の種から、芽ばえ、成長、育成と、一気呵成に大事業構築へと進む仕組みが確立した。科学から一挙に事業化に進むパターンである。しかも、事業拡大も驚く程の早さで進む。こうなると、今までの日本の大企業の研究開発パターン、「有望な技術シーズを探し、産業技術に仕上げる」悠長な流れではとても対抗できない。先を走るスピードが速く、この体制では、追いつけないからだ。 企業外の科学者のアウトプットが鍵を握るから、この問題への対処は、企業だけではできない。そうなると、政治が絡む。 政治が絡めば、議論の輪は広がる。必然的に、産業、学会等の広範な代表の意見が求められる。ところが、代表といっても、自説を主張する人は稀だ。出身母体の審議結果の報告というのが通例。しかも、もともとの審議自体も業界や学会のサポートメンバー作業がベースとなるのが普通だ。 こうした仕組みでは、意見のソースは専門家ばかりになる。結果として、現在の産業構造を前提としたミクロの改良案が沢山提出されることになる。すべての分野から、欧米との比較検討をベースとした「強化策」要望が出される訳だ。これをとりまとめるのだから、所謂「もぐらたたき」以上のことはできない。せいぜい、メリハリをつける位だ。---尤も、新型施策が皆無でも、予算配分のメリハリが大きいと「画期的」と評される。 勝手に批判したが、実はこれだけの作業を進めるだけで、途方もない労力がかかる。結果が単純でも、末端組織が真摯に取り組んだ大労作の集大成なのだ。 実は、これが問題なのである。ミクロの議論が白熱し、マクロ論はなおざりになるからだ。もちろんミクロ論自体は無駄にはならない。それなりの動きが直接的に現れる。実際、橋本政権発では初の大型施策が打たれた。 しかし、本来、議論すべきは、どのような枠組みで技術を生み出すかという問題だ。これについては、議論が低調で、抽象表現でお茶を濁して終わる。各界代表のミクロ論の報告と、実情を勉強していない第三者のコメントだけで、マクロ政策立案は無理なのだ。 こうしたやり方だと、『山奥の林道開発工事助成金』と似た施策立案にならざるを得ない。抜本的な解決策は考えず、当座対応策策定を急ぐのだ。即効性ある、「金」の投入が中心の施策だ。「金」をどこに投入するかという技術論の議論にあけくれる。 無駄な林道工事と批判するのは容易い。しかし、ミクロの経済効果からいえばベスト策かもしれぬ。代替案は簡単にみつからない。 一見、役に立ちそうな科学技術振興策だが、こうした政策とは五十歩百歩だ。効果を考えて一番重要な箇所に金を投下するだけのことだから。 「金」をどこにどれ位注ぎ込むかを議論して、過疎地の産業育成は解決しまい。科学技術も、同じこと。弱体部分を強化するために、有望分野を専門家に考えさせ、資金を重点投入しても、事態の打開が可能という保証は無い。 もともと、日本は科学領域の人材層が薄い。比較的人材が厚く見える分野でも、「基礎」と称した既存知識再整理型学問が多く、極めて浅い内容が中心だ。政策的に強化が図られきた科学分野、ビッグ・サイエンスも極く一部だけである。 貧弱な施設と僅少な予算の研究から脱する必要があるのは確かだが、出発点はここではあるまい。そもそも、産業に役に立つアウトプットがでていれば、こうした状況になる筈がなかろう。企業が役に立つと思えば、仕組みを乗り越えて、利用の方法を考えていたと思う。 今の施策を続けると、科学振興策も『山奥の林道開発工事助成金』と同様の効果しか得られない可能性がある。施策の目的と課題を長期的な流れのなかで、はっきり位置付ける必要があろう。 例えば、誰でも思いつく質問にすら満足に回答できないのが、現在の施策といえよう。---「科学振興のために、年間1000人レベルの博士を産む体制をつくる必要はあるのか?」「海外の有能な研究者招聘を梃子に、新機軸の研究を進める必要はあるのか?」等々。 政治への発言の目次へ>>> トップ頁へ>>> |
|
|
(C) 1999-2004 RandDManagement.com |