目次
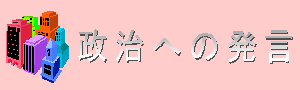
2016.1.9
「夫婦別姓」裁判について
最高裁「夫婦別姓」否定判決の論理はどういうことか知らぬが、調べる気もしない。意見の類もほとんど目を通してはいない。年が明けて、そろそろ忘れた頃になっただろうから、それについて書いてみたくなっただけ。・・・と、もしも有名人が語ったら、多分、別姓推進派からも、家族解体阻止派からも、槍玉にあげられること必定では。それが我々が住む世界である。
それはともかく、小生は、判決報道を見て、思わず、大昔の伊藤整の猥褻裁判を思いだした。
D.H.ロレンス:「チャタレイ卿夫人の恋人」の翻訳本が、性愛小説とか、猥褻本の類とされ、物議を醸したのである。リベラル系は西欧の物真似で権力の横暴はけしからぬと動いたようだ。「モノ真似」と見なすと烈火の如くお怒りになるだろうが、いかにも"えげつない"ムハンマド諷刺画を擁護する気概があるかネということ。
ともあれ、当時の新聞も大騒ぎだったようだ。だが、はたしてどれだけの人がこの小説を完読したものやら。
面白い筋とも思えないし、性的興奮を覚えるような描写がある作品とはとうてい思えないからだ。
・・・そうそう、この手の発言も、槍玉にあがりかねないから滅多に口にする人はいまい。
そう考えるのは、どう見たところで、これは反キリスト教の書だから。キリスト教徒人口が本当に1%も存在しているのか疑問に感じるような社会で、この手の本に人気が湧く理由が小生にはわからぬ。
聖書の宗教観に疎い人が、いくら読んだところでたいした価値はないと思うが。ロレンスはドストエフスキーとは違うのである。言うまでもないが、当時の人々の階級闘争感とは無縁な書ということ。「個人間及び階級間の親密な人間的触れ合いの困難さの探求」[エスターフォーブス,増口充訳]話と考えることはできるとはいえ。
小生から見れば、適切な例とは言い難いが、古事記以前的社会の発想から、キリスト教公認「愛」の倫理感を批判しているような書。
どう考えても一種のパンクである。
なにせ、主要登場人物がふるっている。
【夫】上流階級の車椅子生活者[傷夷軍人]クリフォード卿
【専属介護者】ボールトン夫人[寡婦の看護婦]
【妻】"レディー"たるコニー(コンスタンス)
【愛人】労働者階級の森の猟場番人[雇われ人]
そして、冒頭の文章も大笑いモノ。
Ours is essentially a tragic age, so we refuse to take it tragically.
The cataclysm has happened, we are among the ruins, we start to build up new little habitats, to have new little hopes.
要するに、宗教的には、ついに喜劇の時代に入ってしまったと慨嘆しているようなもの。
クリフォード卿とは、ブリックス&モルタル時代ならぬ、石炭&戦争用銑鉄の時代のリーダーの象徴であるのは、読めばすぐにわかる。そして、それは、すでに不能化しているとの暗喩。
にもかかわらず、文化芸術の領域では、そのような人達の感覚が依然として支配的。と言っても、上流階級出身者でさえ、その精神的迫力の無さで愛想尽かしと相成っている状況。
だが、かろうじて形としての「家」は残っているのである。それを護るため、チャタレー家の妻は跡継ぎを作るお務がある訳だ。上流階級から後腐れ無き種を頂戴せねばならぬのである。
そんなルールに価値を見出す時代がそろそろ終わりを告げつつあったということ。
このような崩れつつある社会での宗教とは、所詮は、こうした社会で生きるしかない人々のための精神的安定剤でしかないと、ロレンスは痛烈に批判している訳だ。
新たな社会における信仰の基底には、性愛あってしかるべしということでもあろう。それは、ひとえに森という自然に帰ることでもある。第10章でのここらの描写は圧巻である。(以下は、労働者階級とコミュニズムについてと、家を護るために子供を授けておくれ、といった会話に引き続く部分からの抜書きである。)
ひっそりと静まり返った灰色の木々・・・
ハシバミの雑木林は実にたくさんの、茶色の弦のような枝・・・
背高の猛々しいブルーベルが生い茂り大きなモスグリーンの葉を日蔭の地面に伸ばしていた。・・・
どうして人はただ単に頑健なだけなのだろうか?オークの木々さえ実に柔らかく小さな、茶色がかった手を持ち、大気を感じ、柔らかな大気に触れているというのに。[初稿:増口充訳 彩流社 2005年]
これだけではわかりにくいが、大自然たる森を護ろうとの現代のエコ思想や、特権階級だけだった自由を万人に、さらには動物にもというリベラル思想とは根本から異なっている点が特筆もの。現代社会の倫理感に真っ向から対峙したと言えよう。(ヒトと森との一体化的信仰感覚を提示していると言ってもよかろう。その象徴が性愛でもある。)
神から全権を委任されたヒトを支配者と考える思想へのアンチテーゼそのもの。
話が長くなったが、「夫婦同姓」という伝統を護れという主張になんの根拠もないということ。古代、貴族は通い婚だった訳だし。
「姓」とは、農民の閉鎖的統制社会制度に合わせ、上流階層の制度を強制的に全員へと広げたものにすぎまい。その本質は、本家-分家-親戚-縁戚の緻密な管理社会の一制度ということ。士農工商的支配と、仏教寺院による住民簿の登記管理をするのに便利な仕組みという以上でも以下でもあるまい。事績的由緒があるものなど、ほんの僅かなのだから。
今でも、地方はその制度の残滓だらけだが、全体的に見れば崩壊一途なのは明らか。「姓」の問題だけとりあげたところで、その流れが変わる訳ではない。
がんじがらめ制度の社会で暮らすのが不快だから、そこから脱出する人が多いだけの話であり、制度の末梢的な部分を護ったからといって、どうにかなる筈もない。それに、それがかえって期待とは逆向きに働く可能性もあるし。
マ、それは、士農工商残滓社会のなかで生きている人々にとっては、不安そのもの。「家」がレゾンデートルなのだから、その気持ちはいかほどか。換言すれば、ついに「同姓」でしか、家族や親類縁者との絆を示せなくなってきたことを意味する訳で。
しかも、民主党政権の置き土産である国民背番号制がついに開始とくる。個人識別は「姓名」ではなく、国家から与えられた「番号」に替わってしまったのだ。対外的に旧姓を使おうが、どうということもない時代の幕開け。地域や家の旧習に「縛られず」、世界に自由に羽ばたく道を歩むことを、国家が容認したということ。
これが時代の流れ。
政治への発言の目次へ>>> 表紙へ>>>
(C) 2016 RandDManagement.com