|
【古都散策方法 京都-その20】
二条城で狩野派の思想を読み取る。
〜 金色装飾を見るなら二条城二の丸である。 〜
「陰翳礼賛」の話をしたら、金地の障壁画について語らない訳にはいくまい。
“大きな建物の、奥の奥の部屋へ行くと、もう全く外の非回が届かなくなった暗がりにある金襖や金屏風が、幾間を隔てた遠い遠い庭の明かりの穂先を捉えて、ぼうつと夢のように照り返してゐるのを見たことはないか。
・・・あれほど鎮痛な美しさと見せるときはないと思う。”というのだから。
 となれば、何所かといえば、それはもう二条城の二の丸しかなかろう。33室、総面積800畳、の襖と壁のほとんどが金色なのだから。
となれば、何所かといえば、それはもう二条城の二の丸しかなかろう。33室、総面積800畳、の襖と壁のほとんどが金色なのだから。
→
「元離宮二条城 障壁画」 (C) 京都市文化市民局
江戸城の内装が残っていれば面白かったのだが、そうはいかない。このような室内装飾がこれだけ大量に完全な形で残っているのはここだけ。
何故残ったかといえば、ほとんど使っていなかったから。 家康が“政治的”意向で平城を構築したのが1603年。家光が天守閣と二の丸という構成にまで発展させ、御水尾天皇行幸(1926年)と家光入城(1634年)。
その後はほとんど使わずじまい。部屋が傷む訳がない。ただ、庭は荒れ果てていたに違いなく、今見るものが当時と同じだったかはわからない。
言うまでもないが、装飾担当は若き狩野探幽一門。全体統括は小堀遠州。
この布陣が谷崎の美学に沿ったものを作ると思えるかな。はなはだ疑問。
と言うことで、少し考えてみようか。
〜 二の丸とは新美学の押し付けが目的だったのではないか。 〜
さあ、それでは、どうしてそんなことを考えたかご説明しよう。
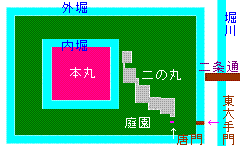 まず、この城の全体だが、それほどのものではない。
まず、この城の全体だが、それほどのものではない。
巨大建築とされるが、同時期の欧州の王城と比較すれば、広大とは言いがたいし、防衛用の城砦としてみても、内堀はあるものの、弱小なものである。
聞くところによれば、南北の軸がずれているそうである。磁石で方位を決めたからというのだ。
おわかりだろうか。
この城は世界標準を意識して作られたものだったのである。
そう思って地図を眺めると、構想がよくわかる。二条通の正面に天守閣が位置しているではないか。威容が際立つように、通りも設計されたに違いない。欧州の王城と同じような発想である。
もちろん、これだけではない。
細い廊下で各種建物を繋ぐのではなく、全体を一つの建物のようにした点もあげてよいだろう。日本の王朝の建物の基本は床張りで、移動式の衝立等で仕切るものだったのを、明確な部屋割りにしたのだ。
そして、それぞれの部屋毎に、戸、壁、天井すべてを統一的なデザインでまとめる。当然ながら、権力者のシンボや、領土の特徴を示す絵画を用いた装飾
となる。なんといっても、特徴的なのは、会見用の大広間を作ったこと。多人数を室内に入れ、公式儀礼を行うことが政事の中心になったということ。
さらに注目すべきは庭園。小堀遠州が“神仙”調で作庭したとされているが、重要なのは、新しく「人工」に景色を作りだした点。おそらく、天守閣も映えるように設計されたに違いないのである。
こんなことに注目するのは、ここはもともと皇室の儀式用の都のための「神泉苑」だったからである。そのための行幸用建物や、祈祷用の施設があったと思われるが、すべて撤去されてしまった訳である。(祇園祭は本来は「神泉苑」で行われるべきものなのかも知れぬ。)
早い話、これは京都の旧来の為政者達に新時代の到来を見せ付けるための建造物ということ。
もしかすると、旧勢力の美感を逆撫でするようなものだったかも知れないのである。それが、家光入城後ほったらかしにされた理由の一つかも。
〜 狩野派の凄味は全体構想力だと思う。 〜
要するに、幕府が作り出す文化は、世界に比べても遜色ない水準であることを見せ付けたのである。
だが、それを、金地に岩絵の具の絵の豪華さとか、手の込んだ彫刻といったものだけで見てしまうと、狩野探幽一門と小堀遠州の構想力が見えてこない。
下手をすれば、豪壮さを打ち出しただけと見てしまう。
例えば、全てが金色の部屋という訳ではない。一番奥の将軍の私的な場所は金色を排除している。しかも、日本の花鳥風月の色彩も消したのだ。
これを理解しないと、ブルーノ・タウトの日光陽明門評のようになってしまうのである。
(ちなみに、探幽は桂離宮と日光陽明門の両方に係わっている筈である。片方がキッチュで、他方は涙が出るほど美しいということがあり得るものかな。)
入り口から、この門を経て、中に入るに従って色彩が変わっているのであり、そこがこの建築の肝である。タウトは意図的に無視したが、滅多に見かけない門なのである。派手な色使いで忘れがちだが、陽明門の色の基本は白である。そこからは、「神」となった家康公の聖なる領域ということ。
おわかりになるだろうか。
将軍は「神」に匹敵することを示すためのデザインがあるのだ。もちろん「神」といっても、それは日本の伝統的なものではなく、儒教的な世界の「天帝」。徳をつんでおり、仙人の力を借りることさえできるということなのだと思われる。
そう、これも世界標準そのもの。つまり二条城とは、王城なのである。
そんな建物が大政奉還の舞台になったのだから皮肉なものである。
そんなことを考えながら、二条城二の丸を拝観するのも面白いのではないか。
ただお勧めすべき場所と言えるかはわからん。ここは修学旅行で必ず立ち寄る場所であるからだ。三々五々でなく、人が塊が動くから、落ち着いて部屋を見ていられないかも。しかも、生徒達の一番の関心事項は“うぐいす張りの床”であり、騒がしいことおびただしい。
ただ、有難いことに、見れない部屋は一部でしかないので、人が分散すること。それに室内は撮影禁止なので人が溜まったりしない。それでも団体さんに出会うとどうしようもないから、じっくり見たいなら朝一番に行くに限る。目と鼻の先にある京都全日空ホテルに宿泊するのも手か。そこまでして鑑賞する気になるかは、考え方にもよるが。
〜 門は秀吉流の王城スタイルにしたかったようだ。 〜
と言うことで、入り口から順番に、小堀遠州と狩野探幽の意図を見ていこうか。
■東大手門・番所■
■唐門■ 伝伏見城。
■車寄■ 伝聚楽第建築物。
外堀から入場するのだが、城砦の櫓門でどうということはない。入ると、南に行けば二の丸で、北に行けば本丸となる。おそらく、仲間内と見なされない勢力は北側はいけなかったと思われる。そこは小型とはいえ武力の拠点であるから、情報漏洩を嫌った筈。
それだけではない。行列は二の丸御殿に行き着くまで、何回も方向転換させられ、は相当時間がかかるようになっている。狭い王城で、長い専用道路や王城前の視界が開けた広場はないが、世界標準の、訪問する気持ちを高める仕掛けと言ってよいだろう。
(1: 西行) 二条通・堀川越え・・・威容を誇る天守閣に近づいていく。
(2: 南行) 堀川通・・・外堀沿いに石垣と城砦建築を眺めることになる。
(3: 西行) 東大手門・・・門前の広場で新たな気構えを要求される。
(4: 南行) 場内・・・城内に入った気分を味わうことになる。
(5: 西行) 唐門前・・・御殿に入る前に身支度を整えることを要求される。
(6: 北行) 唐門から車寄・・・装飾をじっくり眺めることになる。
唐門と車寄が秀吉の遺構であることも、大きな特徴である。武家の時代に入っていることをはっきりと知らしめたのである。
これらの建造物の特徴は、派手なこと。先ずは、入り口で驚かされる訳だ。これでもかというほど、手の込んだ彫刻が組み込まれている。しかも、花蝶鳥、はては仙人まで、なにがなんだか。
そして極めつけは弾けるような彩色。
公家の“雅”文化とは違うというデモンストレーションである。谷崎が感じたように、確かに、日本建築の肝は屋根なのである。
唐門は頭でっかちだが、それこそが目的でもある。その巨大な屋根の構造にみっしりと彫刻を詰め込んでいる訳だが、それは近くでないとわからない。遠目でわかるのは、屋根がもたらす、全体のバランス感の特殊性。
車寄にしても、単なる広い玄関に豪華な欄間というだけでは、特徴が見えまい。違いを際立たせているのは、“唐様”と名付けられた屋根の形状。直線ではなく、雲の絵のような曲線というにすぎない。当たり前だが、これは唐のデザインではなく、日本発である。そんな形式を、大寺院の玄関の定番にさせた訳だ。(歌舞伎座や古い銭湯建築でも玄関に唐破風形式が用いられているのも面白い。京都で有名なのは、大正期創業の船岡温泉。小生は行ったことはないが。)改まった席がある玄関の屋根とはこういうものという通念をつくりあげようとしたのではないか。皇室の正式な建物は平入りで直線的な意匠なので、それと正反対の形態にしたかったということでは。強烈なアンチテーゼである。
面白いのは、唐門と車寄は伏見と聚楽第からの移設とされている点。秀吉が後揚成天皇の聚楽第行幸を行った先例を活用しただけだと思う。
〜 公家の教養主義を嫌ったのではないだろうか。 〜
政治のスタイルを変えようと図った点も注目すべきだと思われる。将軍の威光を際立たせる意図とされているが、その通りだとはいえ、それは公家文化の考えてきた威光とは似ても似つかぬもの。
それが一目でわかるのが、受付・控え部屋(遠待)と為政者の執務室(式台)である。
■遠待■
【勅使の間】
上座は、床の間と花の絵入りの違い棚付き。
上段が金地の源氏雲。緑と朱の葉の青楓に緩やかな水辺の景色(初夏)
下座は檜の並木。
【一・二・三の間】大名控えの間
俗称「虎の間」。金地に、竹林に虎と豹(雌虎)
水を飲む穏やかなシーン。その一方で、狙い定め動き出す体勢のシーンも。
【柳の間・若松の間・芙蓉の間】
■式台■
【式台の間】
松の古木。
【老中一・二・三の間】
雁(春〜秋)
なかなか面白いのは、玄関から勅使の間に入るには、一・二・三の間の際を通ってぐるっと回っていくしかないこと。上座は公家で、下座がお付だが、帳台は他から入れないから、実用性はない。一見、公家重視に見えるが、力などないからこんなところで十分ということ。部屋の装飾は、公家が好むといわれる“雅”とされる楓や花となっていると言われているが、逆撫でするようなものではないか。
貴族の好む楓や花とは、その絵自身ではないからだ。それは単なる象徴であり、その裏に流れる意味があって始めて美しさになる。ところが、狩野派は絵そのもので迫っているのである。
“雅”とは絵が繊細ということではなく、それを意味する和歌あるいは漢詩あってこそ。場合によっては説話や絵巻物の一シーンかも知れないのである。何の説明もないが、それを絵柄から読み取る力がないと鑑賞できない訳だ。
それが否定されたということ。
逆に、老中の間でわかるように、武士が“気高き”存在であることを示したものが、日本古来から連綿と続いてきた深い森のイメージを被せた装飾である。言葉の遊びを越えた感慨を与える作品を狙ったと見てよいだろう。
ただ、虎の絵で威圧感を与えたとの解釈だけはいただけない。だいたい、水を飲む絵など、小生はほのぼの感があるように思うが。それに、老中執務側の装飾と比べれば、簡素であり、それほど重要視していたようにも思えない。従って、この絵は縁起担ぎと見た。そうでなければ、屋敷の入り口に虎の屏風を立てる風習が広く根付く筈がなかろう。
そもそも、当時の人々は毛皮の虎しか知らなかったのだから、恐ろしさというより物珍しさが先に立つ筈だ。要するに、人気図柄。そんな感覚がわかるのは、後ででてくる大広間登壇の待ち合わせも間の名称。「蘇鉄」と名付けられているが、コレ、まごうかたなき外来植物。だからこそ嬉しかったのである。公家社会の狭い視野を捨て、世界の視点で考えていこうという姿勢があったのである。虎の絵とは、その点で象徴的。
だいたい、玄関前の狭い部屋が霜がおりた柳老の冬景色。これが威圧感である訳がなかろう。ご存知のように、正月に使うのが柳箸。もっとも、本物は高価すぎるので名前だけのものが多い。何故、柳かといえば、折れないから以外に考えられまい。まさしく縁起かつぎそのもの。
ちなみに、家康が一番気にしそうな岩清水八幡宮の供花は、中心が松と竹。その隣が牡丹と梅。その他は、橘、菊、桜、南天、杜若、椿、紅葉、水仙で、全12種。柳は無い。
松と竹を重視するのは当たり前。
〜 会見場の松づくしは見事である。 〜
将軍の公式対面所である一の間(上段)・二の間(下段)が二の丸の最重要な部屋である。下段の大名を謁見する儀式の場である。広いし、高さも十分とってあり、流石。その広さを生かした装飾がなされた訳である。四の間は槍などの武器一時保管所とされているが、それは戦争さなかに使用した時の話で、装飾から見て、将軍が一時留まるために使う部屋であろう。身辺警護の武者は帳台に隠れていたと見るべきだろう。式台、大広間、次の黒書院三の間の「松」を見ればわかるが、大広間の一・四の間の絵師の力量が格段に上に感じられるからである。
■大広間■
【一・二の間】
床の間に松の古木。
全面金地に豪壮な松、後に孔雀
【三の間】
孔雀、松。透かし彫り欄間。
【四の間】
鷲と鷹、松に渓流。
■建物繋ぎ部屋(蘇鉄の間)■
広い部屋である。
大広間の威厳を感じるような壮大な松を見た後で、小広間の松を眺めると、その違いがよくわかる。実におだやかな松である。仲間うちの会合であることを絵で表現しているのである。こちらは、親藩の対面所だからだ。後に黒書院と名前が付いたのもわかる気がする。こちらは、いかにも書院らしい風情だし、秀吉が嫌った“黒”というのは言いえて妙。
狩野派の作品をじっくり鑑賞したいのなら、黒書院がお勧め。
→
「文化遺産オンライン」 [狩野派で検索: 3〜11頁] (C) 文化庁
■黒書院(小広間)■
【一・二の間】
梅とつぼみを残した桜(早春)から、満開、散り初めの桜(晩春)。
雌雄の雉。
【三の間】
松鷺等
【四の間】
菊花等(秋の景)
【牡丹の間(東側の板敷広縁)】
紅白の牡丹
“黒”に対して“白”としているのが、黒書院から渡り廊下で繋がる将軍私室兼寝所。すでに述べたように、ここは金色がなくなり、白と黒の世界である。「西湖」を描いたのは、そこが世界最高の景色であり、為政者はその視点で世の中を見る力があるということなのでは。
■白書院(御座の間)■
【一・二の間】
床の間付き。水墨画。「西湖」雪の山水図。
【四の間】
奈良の情景を描いた水墨花鳥図らしい。
ということで私見でまとめてみたが、鑑賞の参考になれば幸。
<<< 前回 次回 >>>
「観光業を考える」の目次へ>>>
トップ頁へ>>>
|
|