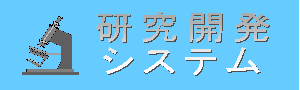
技術マネジメント論 [6] 2006年8月3日
| トップ頁へ>>> |
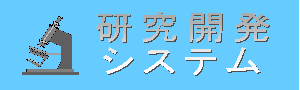
技術マネジメント論 [6] 2006年8月3日 |
「研究開発」の目次へ>>> |
|
|
技術体系創出の時代…前回は、“知恵を駆使して”ナンバー1の地位を確立することが、最重要課題になったとの話をした。→ 技術マネジメント論 [5] 「ナンバー1を狙う時代」 (2006年8月2日)  間違えてはならないのは、ナンバー1を目指すからといって、QCDの力量向上、開発スピードアップ、しみだし型展開が不要になったという訳ではないという点。
間違えてはならないのは、ナンバー1を目指すからといって、QCDの力量向上、開発スピードアップ、しみだし型展開が不要になったという訳ではないという点。勉強でいえば、70年代の課題は初級編、80年代は中級編、90年代は上級編、21世紀は師範級と言ったらよいだろうか。 比類なき能力があるなら、いきなり師範級の経営を目指すこともありえるが、凡人ならやはり初級から順に極めていかなければ、とても師範級の競争にはとりかかれない。 さて、こんな課題があるとしたら、技術マネジメントとしては、どんな動きになるだろうか。 先ず、70年代の、QCDの質を高める方針から考えてみよう。 この方針は、当時の感覚で考えれば、KAIZEN(改善)活動やQC運動の徹底と同義と言ってよいだろう。 方法論では、“7つ道具”とか、実験計画法ということになる。 方法論の導入は確実に成果をあげた。品質向上が、コストダウンにも結びついたりしたからである。 常識からいえば、品質向上に労力を使えば、コストアップになる筈なのに、実際にはコストがどんどん下がったから、日本企業のマネジメントが注目され始めた頃である。 欧米流の品質管理は、不良品をどうはじくかという発想だったが、日本流は不良品の発生原因を叩くことに力が注がれたから、こんな現象が発生したとも言える。 こんなことができたのは、“フィッシュ・ボーン”型問題整理技法が、グループ活動の質的向上に寄与したことが大きそうである。 但し、こうした手法導入が切り札になったとは思えない。手法を習いながら、徹底した議論が行われたことが奏功したのだと思う。 現場で、文字通り、文殊の知恵を集めることに成功したから大きな成果に結びついたのである。要は、グループ活動を通じて、直面する課題をはっきりさせ、実践的な解決策を案出し、すぐに実行に移れる仕組みを作った企業が絶大な競争力を発揮したのである。  しかし、80年代に入ると、技術も市場も変化のスピードが早くなった。QCDの力量差だけでは、とても勝てる気がしなくなってくる。 現実に、先を走る企業が羨ましいほど高収益をあげているのに、波に遅れた企業は、薄い利益しか得られないことがはっきりしてきた。 開発のスピードアップに注力せざるを得なくなったのである。 当然ながら、開発プロセスを見直すしかない。 今迄のように、狭い範囲で、現場の力に頼っているだけではなにもできないことになる。企業組織全体で考える必要に迫られたのである。 大変身を要求されたに等しいのだが、日本企業の場合は、従業員が終身雇用で、ゼネラリストが多かった。従って、QC活動と同じパターンで、組織の壁を越えて新しい仕組みをつくる動きがすぐに始まったのである。要するに、企画から、生産、販売まで、情報を交換しながらタイミングよく進めれば、開発のスピードアップなど、それほど難しいことではなかったのである。 組織の壁を越えた動きに違和感がなかったことが大きいが、それ以上に、現場のグループ活動が定着していたから、新たなプロセスの合わせて仕事の進め方を変えることが、現場レベルですぐに対応できたことが大きい。 欧米から見れば、こうした日本企業の組織能力は垂涎の的だった。とても真似できるものではないと感じた企業も多かった。 しかし、その強さも、グローバル化になると通用しなくなった。 先が読める競争ではなくなったからである。 要するに、同質の競争で、質、コスト、速度で競争相手を上回ったところで、違う土俵に持ち込まれると勝てないということである。 今までの力を活かすには、変化に対して迅速に変身するしかない。新たな土俵が作られたら、そこで勝つための能力を急いで作り上げるという訳だ。 その程度なら、日本企業も組織力でなんとかなるからだ。 しかし、迅速対応といっても、それは結局のところ後追いであることには違いない。勝てる根拠は乏しい。 そこで、その根拠を求めることになる。 日本企業の場合、そんなものは技術しかない。そこで、他社を凌駕できる技術の構築が最重要課題になったのである。名付けて“コア技術”である。 一旦、この技術領域が決まれば、いままで培ってきた組織能力が生きてくるのである。 勝てる技術であるから、飛躍できそうなチャンスが見つかれば、即座に組織的に対応できるようになる。新たな“土俵”が登場してきても、自社の強みを生かして乗り込むから、多少遅れても、十分戦えるのだ。 自然な形で、強い既存領域から、強みが発揮できそうな領域へとビジネスが広がっていくのである。“しみだし型展開”と呼ぶ所以である。 武器とすべき技術領域をはっきりさせる経営が求められた訳である。 弱い技術や、効率が悪そうな領域は切捨てざるを得ないということでもある。 この流れを、単純な効率向上のスリム化と考えた企業もある。短期的には収益性は向上するが、コア技術強化に必要な機能までカットしてしまえば、当然ながら競争力は低下する。コア技術は何かが見えている企業とそうでない企業の格差がつくことになる。 そして、21世紀。 ナンバー1の地位を目指す競争の時代である。 こうなると、コア技術領域なら競争できる、といったレベルでは実現できるとは言えなくなる。 武器になる技術があるというだけではなく、そうした武器をどう使うとナンバー1の地位を射止めることができるか知恵を出すしかないのである。 誰も考えていなかったような新機軸で展開するしかないのである。 こうなると、知恵がでそうな領域で戦うしかない。純技術的な視点からみた“コア技術”に頼るのではなく、“コア技術”を生み出した根拠となった組織能力や、“コア技術”を上手く使って勝つ能力を、まとめあげて武器にするしかない。 これこそが“技術体系”なのである 当たり前だが、他社の真似などできないし、頭のなかで体系化したところで意味はない。“技術体系”とは、技術で勝つための知恵を創出する組織能力を技術で定義しただけの話だからである。 「研究開発」の目次へ>>> トップ頁へ>>> |
|
|
(C) 1999-2006 RandDManagement.com |