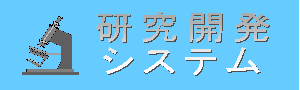
技術マネジメント論 [10] 2006年8月21日
| トップ頁へ>>> |
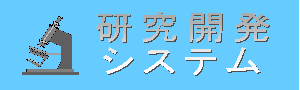
技術マネジメント論 [10] 2006年8月21日 |
「研究開発」の目次へ>>> |
|
|
分析思考からの脱却…第1回〜第9回は“序”にすぎず、じっくり考えて欲しいのはここから先、と思わせぶりな話で終わった。→ 技術マネジメント論 [9] 「オープン化の時代」 (2006年8月9日) なにを言いたいかといえば、こんな一般論をいくら検討したところで、直接的には、たいして役に立たないということ。 しかし、まんざら役に立たない訳でもない。 時代の流れが感覚的にわかったからといって、それで、対応策が見つかると思ったら、大きな間違い。しかし、対応策を思いつくためには、時代感覚が重要ということなのだが、この理解が結構難しいのである。 どういうことか、最近のトピックスで考えてみよう。 2006年8月に入って、突如として、経済ニュースの中心がTOB になってしまった感がある。といっても、もっぱら、経営権争奪戦の話である。 それはそれで、株主にとっては重要な話だが、関心が経営権に偏りすぎている。これでは、買収にせよ、独立維持にせよ、今後、どう道を切り拓いていくつもりかさっぱりわからぬ。 政治分野でも同じだが、どのように多数派工作が進んでいて、誰が権力を握るかなど、たいした問題ではない。我々が知りたいのは、どのような方針で、その方向に進もうとしていて、その結果どうなりそうか、という点である。しかし、そんな解説は滅多にお目にかからない。これが日本の文化なのかも知れぬ。 こまったものだ。 それはともあれ、ニュースで驚いたのは、メイン行の状況。 「製紙業界の現状を踏まえた成長戦略を何度も提案していた。にもかかわらず、王子による北越買収のニュースは寝耳に水」(1)だったという。 このことは、“現状を踏まえた成長戦略”とは、国内産業の構造には手をつけない代物でしかないことを示唆している。国内の業界変動をできる限り避け、余力を、伸びている海外市場に手を出すという程度の発想だったのだろう。 要するに、その程度の対処で十分生き残れるという見方である。 何故、時代認識が重要かといえば、そんなことでよいのか、という疑問がふつふつと湧き上がってくるからに他ならない。 生き残りのために、ナンバーワンの地位をどのように確保するか、必死に知恵を絞っている企業を見ていれば、なおさらである。 フタタの件も見てみよう。 こちらは、市場は縮小一途であり、団塊世代退職でその流れが強まりそうな気配だ。そんな環境だから、「業界で生き残るには、他社と合併した方がいい。」(2)という点では異存がないようだ。“残り物には福”まで頑張る気なら別だが、徹底的な合理化を進めるしか生き残り策が見つからないということだろう。 こんなことは今わかったことではないと思うが。 ただ、「店舗の従業員の整理による失業者の山」(3)だけは避けたいということで、動くに動けなかったということのようだ。地域経済全体は低迷しており、不採算店が好転するとも思えないが、業種転換を図るべきかが論点だったようだ。 要するに、抜本的な解決は、乱を招くから、できる限り避けたいのである。 このような動きを見ていて、90年代、経営コンサルタントの内輪の集まりでの、石油メジャーCEO の講演内容を、つい思い出してしまった。 印象的だったのは、先ずは時代認識ありきだった点。 石油メジャーは膨大な利益を出していたが、それは上流が安泰だったころの話。 昔なら、税金が高い国での下流ビジネスに期待などしていなかったが、上流で地位を失ったから、そうは言えなくなったのである。突然、全てが変わった。生き残りのためには、大改革は不可避。時間の余裕はない。一歩間違えれば没落必至。 この認識が出発点である。 この認識がなければ、コモディティ商品だから、合理化の徹底追求で終わりかねないのである。これでは、なにも変わらない。 それでは、何をしたか。 上流の採掘側ではハイテク探鉱・掘削技術力の強化と、既存油田の効率アップが至上命題となる。そして、下手をすると息を止められかねないから、事故防止の仕組み作りに邁進する。当然だが、下流ビジネスとの分離も進めた。上流で規模の勝負ができないのだから、一番儲かる顧客に原油を販売するのは自然な流れである。スポット市場参加の道を選ぶことになる。 一方、下流のガソリン販売側も、これに合わせた動きをとることになる。社内外を問わず、一番安いオイルの調達に励む。同時に、競争相手に負けない、徹底的なコスト削減も不可欠だ。規模の経済が効くなら、合併だろうが、TOBだろうが、友好的だろうが、敵対的だろうが、やるしかない。 これこそが、企業経営の合理主義である。 言うまでもないが、ここで非合理的な判断を下し、経済原則を無視すれば、衰退の道を歩むことになりかねない。 もっとも、これは“言うは易し”の世界である。 世界の覇者と呼ばれていた日本の家電・半導体産業の動きを思い出すと、その難しさがわかる筈である。 アナログからデジタル化の流れは皆わかっていた。アナログ技術者をザクッと切り捨てた家電企業もある。一見すれば抜本的な動きに映るが、家電産業がどう変わるのかは示さなかった。相変わらず他社類似の新製品が並ぶだけ。売り方も何も変わらない。 一方、アナログ技術者を残した企業も、デジタル化にどう対応していくのか、はっきり描こうとはしなかった。 結局、両者とも、何をしたかといえば、製品差別化への邁進と、次世代商品開発への注力だけである。以前とどこか変わっただろうか。 同じような製品を作るだけでは利益が出なくなると言われていたから、やるべきことをやっただけかもしれぬが。 要するに、抜本的な変革などしなくても、力があるから生きていけるとふんだだけの話である。手をつけ始めたのは、凋落が見えてから。そうなってからでは遅いことを知りながら、できなかったのである。 もう少し語ろう。 家電製品の核は半導体とソフトになるということも十二分に“理解”していた筈だ。半導体事業は、開発と生産には、膨大な投資が必要だから、規模の効果が効くことも自明だった。自社内の半導体需要に合わせて生産し、その余剰を市場に流すモデルが成り立たないのもわかっていた。 わかっているにもかかわらず、半導体事業をどう位置づけるか、明確にした企業は少ない。 知識で、世界は変わるとわかっても、どうにもならないことがよくわかる。 口では地殻変動発生と言うが、生存を賭けて動く必要性は感じていないのだ。時代感覚がないのである。 なんとなく不安だが、頑張ればなんとかなると考えている状態と言ってよいだろう。 従って、産業内で波風を立てる動きを避け、社内で“それなりの”対処をすれば十分と考えることになる。環境は大変動するが、社内は小変動でも、上手く行くらしいのだ。 緊張感を欠けば、必ずこうなる。 現在の状況を前提とした最適解を追求して満足してしまうからだ。しかも、狭い視野で考えるから、先は読めないし、何をすべきか曖昧なまま。 懸命に仕事をしていれば、だんだん状況がわかってくるから、それに対処すれば十分と踏んでいるのである。 この状態が続く限り、いくら“優秀”な人材を集めて戦略を練っても、結果は変わらない。計画立案の精緻化や、新しい動きが加わるだけの話で、せいぜいが、美しい戦略書ができあがるだけのこと。 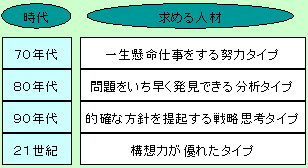 変革が必要だと考えるなら、先ずは、それに合った人材登用しかない。
変革が必要だと考えるなら、先ずは、それに合った人材登用しかない。繰り返し述べてきた、10年毎の変化に当てはめると、どんな人材が必要なのか、自明だろう。 ここで一番重要なことは、分析が優れている人では対応できない時代に入ったという点である。 もちろん、分析能力が弱いと、雑な経営になるから、今でも重要な能力ではある。しかし、この能力だけに頼ると、大きな流れや、構造変化を見逃しかねないということである。 くどいが、日本の家電・半導体産業をよく見て欲しい。 すでに述べたように、過去を学べ、と繰り返したい訳ではない。 現在、技術の流れが大きく変わりつつある。産業構造変化の兆候と見てよいだろう。 しかし、それに対応すべく動いている企業は少ないようだ。 今のままでも、なんとかなると考えているのだろう。 繰り返すが、狭い範囲で精緻な分析を行うということは、“なんとかなりそうだ”という計画を作ることと同義である。それで対処できた時代は終わったのではないか、という時代認識が必要なのである。 そんな時代認識ができれば、ものの見方が変わってくる筈だ。構造変化が見えてくるのである。 分析思考から脱却しない限り、なにをすべきかは何時までも読めないということである。 --- 参照 --- (1) “王子・北越の攻防に動けぬメガバンク、投資銀行業務強化の効果見えず” ロイター [2006.8.14] http://today.reuters.co.jp/investing/financeArticle.aspx?type=economicPolicies&storyID=2006-08- 13T224947Z_01_nTK2902179_RTRJONT_0_MnTK2902179-4.xml&src=cms (2) http://www.nishinippon.co.jp/nnp/economics/20060812/20060812_018.shtml (3) http://gendai.net/?m=view&g=syakai&c=020&no=27768 「研究開発」の目次へ>>> トップ頁へ>>> |
|
|
(C) 1999-2006 RandDManagement.com |