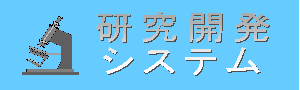
技術マネジメント論 [15] 2006年9月26日
| トップ頁へ>>> |
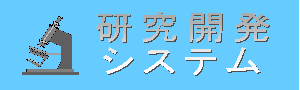
技術マネジメント論 [15] 2006年9月26日 |
「研究開発」の目次へ>>> |
|
|
組織能力と事業観…前回は、“組織能力”を理解し、その能力を活用できる人材を育成することが緊要との話をした。→ 技術マネジメント論 [14] 「組織能力を活かせる人材の重要性」 (2006年9月19日) 言いたいことは、単純である。 底力があると確信しているなら、ベクトルを合わせて本気で取り組めば、飛躍のチャンスはあるというだけの話。 ところが、これができない企業が多い。 そもそも、現状認識からして揃っていないことも多い。しかも、それに気付いていないことさえある。 典型は、自社の強い技術や、弱い技術について意見が割れたりする企業。これは、方法論の問題ではない。技術の素人でなければ、考えればわかる筈なのだが、事業観がバラバラなので議論がかみ合わないのである。 このような企業では、トップが、危機感醸成と称して、我が社は脅威に晒されていると語ることが多い。ところが、本気で改革を始めるつもりと考えると大間違い。脅威といっても、先の問題と見ているだけで、当面は動くつもりはないのである。危機感を言葉で煽れば、組織に“緊張感”が生まれるという目論見なのだ。この言葉に踊らされ、対応策を提言する人もいるが、当然ながら何の動きにも繋がらない。 このような組織に限って、不思議なことに“手法”大好きのことが多い。人材教育に力を入れているつもりなのだ。 言うまでもないが、猫に小判の世界。 しかし、このような組織でも、的確に状況を認識している人はいる。このままでは、一大事と考える人は、黙って準備することになるだけのこと。 日本企業の強みとは、こんな人達を抱えていることかも知れない。 ともあれ、これでは力が発揮できる訳がない。 時代感覚の話をしつこくするのは、こうした状況を嫌と言うほど見せられてきたからである。このままでは、自分達はどうなるのか、議論できる力を身につけない限り、ここから一歩も進めまい。 どうしてこうなるのかは、時代認識を振りかえってもらえば、想像がつくと思う。  話はとぶが、交流相手を考えると、感覚的にわかるかもしれない。世界中の専門家を知っており、何をしているのかわかると豪語する技術屋が、的確な判断ができた時代ではないのである。 技術が強いか弱いかの評価にしたところで、どんな産業構造下で、どのような事業を追求するかがはっきりしなければ、技術の位置付けはできない。位置付けなしで、技術競争力の評価基準を作って、自社の状況を判定したところで、ビジネスに役に立つ訳がないのである。 事業観を欠いていると、議論にならないのだが、それに気付かない人は多い。 おそらく、事業観が自明だった時代に慣れているため、この問題を軽視してしまうのだろう。先ずは、この状態からの脱皮が必要だ。 実は、これこそが組織能力そのものとも言える。 「研究開発」の目次へ>>> トップ頁へ>>> |
|
|
(C) 1999-2006 RandDManagement.com |