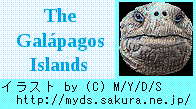| [→表紙]
■ 孤島国JAPAN ■
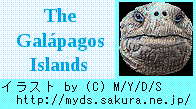
■■■ 日本の色彩感覚の原点 ■■■
 茶と鼠…(20160119) 茶と鼠…(20160119)
 青…(20160113) 青…(20160113)
 白に黒…(20160105) 白に黒…(20160105)
 明暗顕漠…(20160103) 明暗顕漠…(20160103)
 東西南北…(20160102) 東西南北…(20160102)
■■■ 日本語の語彙を探る ■■■
 ヒキ v.s. ガマ…(20150410) ヒキ v.s. ガマ…(20150410)
 コウモリの語源 …(20150403) コウモリの語源 …(20150403)
 蝸牛考々 …(20150401) 蝸牛考々 …(20150401)
 身体の倭語[続々] …(20150328) 身体の倭語[続々] …(20150328)
 身体の倭語[続] …(20150327) 身体の倭語[続] …(20150327)
 身体の倭語 …(20150326) 身体の倭語 …(20150326)
 鳴く䖵…(20150323) 鳴く䖵…(20150323)
 蛇という蟲…(20150322) 蛇という蟲…(20150322)
■■■ 鳥崇拝時代のノスタルジー ■■■  →鳥INDEX →鳥INDEX
 [82]古代鏡の鳥…(20181001) [82]古代鏡の鳥…(20181001)
 [81]迦毛大御神[日本書紀の金鵄譚]…(20180930) [81]迦毛大御神[日本書紀の金鵄譚]…(20180930)
 [80]迦毛大御神[山城の鴨]…(20180929) [80]迦毛大御神[山城の鴨]…(20180929)
 [79]迦毛大御神[飛鳥に不在]…(20180928) [79]迦毛大御神[飛鳥に不在]…(20180928)
 [78]迦毛大御神[事代主命の地]…(20180927) [78]迦毛大御神[事代主命の地]…(20180927)
 [77]迦毛大御神[葛城の鴨]…(20180926) [77]迦毛大御神[葛城の鴨]…(20180926)
 [76]迦毛大御神[意富多多泥古命]…(20180925) [76]迦毛大御神[意富多多泥古命]…(20180925)
 [75]迦毛大御神[阿遅鉏高日子根神]…(20180924) [75]迦毛大御神[阿遅鉏高日子根神]…(20180924)
 [74]鳥居考 [中華門]…(20180923) [74]鳥居考 [中華門]…(20180923)
 [73]鳥居考 [ストゥーパの門]…(20180922) [73]鳥居考 [ストゥーパの門]…(20180922)
 [72]鳥居考 [極楽東門]…(20180921) [72]鳥居考 [極楽東門]…(20180921)
 [71]鳥居考 [精霊門]…(20180920) [71]鳥居考 [精霊門]…(20180920)
 [70]鳥居考 [神社の門]…(20180919) [70]鳥居考 [神社の門]…(20180919)
 [69]鳥居考 [三輪山の結界]…(20180918) [69]鳥居考 [三輪山の結界]…(20180918)
 [68]鳥居考 [序]…(20180917) [68]鳥居考 [序]…(20180917)
 [67]「料理物語」…(20180916) [67]「料理物語」…(20180916)
 [66]烏馬鹿にされる…(20180915) [66]烏馬鹿にされる…(20180915)
 [付録]雀型鳥の分岐図…(20180915) [付録]雀型鳥の分岐図…(20180915)
 [65]飛鳥補遺…(20180914) [65]飛鳥補遺…(20180914)
 [64]Hindu神話の鳥…(20180913) [64]Hindu神話の鳥…(20180913)
 [63]群れて喧しい鳥…(20180912) [63]群れて喧しい鳥…(20180912)
 [62]初夏告鳥…(20180911) [62]初夏告鳥…(20180911)
 [61]鳥の王…(20180910) [61]鳥の王…(20180910)
 [60]カワセミの語源…(20180909) [60]カワセミの語源…(20180909)
 [59]"飛鳥"の由来…(20180908) [59]"飛鳥"の由来…(20180908)
 [58]西王母の戴勝…(20180907) [58]西王母の戴勝…(20180907)
 [57]当初、雀は和歌から排除された…(20180906) [57]当初、雀は和歌から排除された…(20180906)
 [56]カラ類のパトロール…(20180905) [56]カラ類のパトロール…(20180905)
 [55]隠語"夜鷹狩"の広がり…(20180904) [55]隠語"夜鷹狩"の広がり…(20180904)
 [54]鵲の橋"の由来は定かではない…(20180903) [54]鵲の橋"の由来は定かではない…(20180903)
 [53]北京ダックは愛玩…(20180901) [53]北京ダックは愛玩…(20180901)
 [52]反鳥詠み…(20180831) [52]反鳥詠み…(20180831)
 [51]オスプレイの習性…(20180830) [51]オスプレイの習性…(20180830)
 [50]鵯合…(20180829) [50]鵯合…(20180829)
 [49]楚辞 v.s. 詩経…(20180828) [49]楚辞 v.s. 詩経…(20180828)
 [48]隹 v.s. 鳥…(20180827) [48]隹 v.s. 鳥…(20180827)
 [47]風土記断片の鳥…(20180826) [47]風土記断片の鳥…(20180826)
 [46]鵠=ハクチョウ説が妥当…(20180825) [46]鵠=ハクチョウ説が妥当…(20180825)
 [45]出雲國風土記の鳥…(20180824) [45]出雲國風土記の鳥…(20180824)
 [44]播磨國風土記の鳥…(20180823) [44]播磨國風土記の鳥…(20180823)
 [43]常陸國風土記の鳥…(20180822) [43]常陸國風土記の鳥…(20180822)
 [42]鳩は鬱々…(20180821) [42]鳩は鬱々…(20180821)
 [41]純外洋棲の鳥…(20180820) [41]純外洋棲の鳥…(20180820)
 [40]白の吉祥感が確定していない鳥…(20180819) [40]白の吉祥感が確定していない鳥…(20180819)
 [39]日本で囀らない鳥…(20180818) [39]日本で囀らない鳥…(20180818)
 [38]青と橙色の鳴鳥…(20180817) [38]青と橙色の鳴鳥…(20180817)
 [37]揚雲雀…(20180816) [37]揚雲雀…(20180816)
 [36]東京の鳥…(20180815) [36]東京の鳥…(20180815)
 [35]鴎が飛んだ…(20180814) [35]鴎が飛んだ…(20180814)
 [34]古手本格的魚獲水鳥…(20180813) [34]古手本格的魚獲水鳥…(20180813)
 [33]もの悲しさを生む鳥…(20180812) [33]もの悲しさを生む鳥…(20180812)
 [32]春告鳥は土着…(20180811) [32]春告鳥は土着…(20180811)
 [31]反仏教のドラミング…(20180810) [31]反仏教のドラミング…(20180810)
 [30]猫頭鷹の捉え方…(20180809) [30]猫頭鷹の捉え方…(20180809)
 [29]小鳥の猛禽…(20180808) [29]小鳥の猛禽…(20180808)
 [28]鷲鷹類…(20180807) [28]鷲鷹類…(20180807)
 [27]小中華帝国化の象徴たる鳥…(20180806) [27]小中華帝国化の象徴たる鳥…(20180806)
 [26]干潟で鳴き渡る番…(20180805) [26]干潟で鳴き渡る番…(20180805)
 [25]大伴家持御愛好鴨…(20180804) [25]大伴家持御愛好鴨…(20180804)
 [24]愛称を失った小さき鴨…(20180803) [24]愛称を失った小さき鴨…(20180803)
 [23]不倫の象徴カモ…(20180802) [23]不倫の象徴カモ…(20180802)
 [22]味なヤツ…(20180801) [22]味なヤツ…(20180801)
 [21]秋沙考…(20180731) [21]秋沙考…(20180731)
 [20]換羽鳥…(20180730) [20]換羽鳥…(20180730)
 [19]雁が音…(20180729) [19]雁が音…(20180729)
 [18]"野生命"の弱き鳥…(20180728) [18]"野生命"の弱き鳥…(20180728)
 [17]百済を想い起こす林禽系渡り鳥…(20180727) [17]百済を想い起こす林禽系渡り鳥…(20180727)
 [16]林禽系の大集団渡り鳥…(20180726) [16]林禽系の大集団渡り鳥…(20180726)
 [15]松の実喰い…(20180725) [15]松の実喰い…(20180725)
 [14]可愛い潜り鳥…(20180724) [14]可愛い潜り鳥…(20180724)
 [13]鳥占の鳥…(20180723) [13]鳥占の鳥…(20180723)
 [12]愛の鳥…(20180722) [12]愛の鳥…(20180722)
 [11]托卵系はゴチャゴチャ…(20180721) [11]托卵系はゴチャゴチャ…(20180721)
 [10]越の雉…(20180720) [10]越の雉…(20180720)
 [9]古代感がある鶉は、和歌のモチーフに…(20180719) [9]古代感がある鶉は、和歌のモチーフに…(20180719)
 [8]山鳥は独り寝の習性とされてきた…(20180718) [8]山鳥は独り寝の習性とされてきた…(20180718)
 [7]雉は鳴かずにいられぬ…(20180717) [7]雉は鳴かずにいられぬ…(20180717)
 [6]燕は特別扱いだが土着的情緒を欠く…(20180716) [6]燕は特別扱いだが土着的情緒を欠く…(20180716)
 [5]庭つ鳥への想い…(20180715) [5]庭つ鳥への想い…(20180715)
 [4]鵜を尊ぶ風習が残るのは倭だけ…(20180714) [4]鵜を尊ぶ風習が残るのは倭だけ…(20180714)
 [3]国家観が生まれると、鳥信仰は消えるのかも…(20180713) [3]国家観が生まれると、鳥信仰は消えるのかも…(20180713)
 [2]律令国家体制下では単なる鳥…(20180712) [2]律令国家体制下では単なる鳥…(20180712)
 [1]大雀命…(20180711) [1]大雀命…(20180711)
■■■ 本邦蜘蛛文化 ■■■ →蜘蛛INDEX
 クモの語源…(20180531) クモの語源…(20180531)
蜘蛛をこよなく愛した人々
 [25]"蜘蛛の囲"は夏の季語…(20180619) [25]"蜘蛛の囲"は夏の季語…(20180619)
 [24]蜘蛛の恩返し…(20180618) [24]蜘蛛の恩返し…(20180618)
 [23]桶職人の蜘蛛嫁話…(20180617) [23]桶職人の蜘蛛嫁話…(20180617)
 [22]蜘蛛婿入譚は古代の山信仰か…(20180616) [22]蜘蛛婿入譚は古代の山信仰か…(20180616)
 [21]駄洒落の対象…(20180615) [21]駄洒落の対象…(20180615)
 [20]弦楽器をモノする妖怪だが…(20180614) [20]弦楽器をモノする妖怪だが…(20180614)
 [19]賢いと褒めてくれた水神…(20180613) [19]賢いと褒めてくれた水神…(20180613)
 [18]蜘蛛網的世界観の時代があった…(20180612) [18]蜘蛛網的世界観の時代があった…(20180612)
 [17]ササガネ考…(20180611) [17]ササガネ考…(20180611)
 [16]漁網を教えてくれた南島の神…(20180610) [16]漁網を教えてくれた南島の神…(20180610)
 [15]細蟹挽歌…(20180609) [15]細蟹挽歌…(20180609)
 [14]蜘蛛は女系的通い婚時代のチャーム…(20180608) [14]蜘蛛は女系的通い婚時代のチャーム…(20180608)
 [13]"蜘蛛手"表現が好まれた…(20180607) [13]"蜘蛛手"表現が好まれた…(20180607)
 [12]七夕の日の蜘蛛網占い…(20180606) [12]七夕の日の蜘蛛網占い…(20180606)
 [11]蜘蛛は稲作民族の太陽だったのかも…(20180605) [11]蜘蛛は稲作民族の太陽だったのかも…(20180605)
 [10]遊糸見て、嬉し…(20180604) [10]遊糸見て、嬉し…(20180604)
 [9]心に沁みる蜘蛛の仕事ぶり…(20180603) [9]心に沁みる蜘蛛の仕事ぶり…(20180603)
 [8]"蜘蛛の糸巻"…(20180602) [8]"蜘蛛の糸巻"…(20180602)
 [7]住吉大明神と長谷寺観音のお遣い…(20180601) [7]住吉大明神と長谷寺観音のお遣い…(20180601)
 [6]万葉仮名に蜘蛛を起用…(20180530) [6]万葉仮名に蜘蛛を起用…(20180530)
 [5]古今著聞集の蜘蛛譚…(20180529) [5]古今著聞集の蜘蛛譚…(20180529)
 [4]今昔物語集の蜘蛛譚…(20180528) [4]今昔物語集の蜘蛛譚…(20180528)
 [3]和歌の世界を徘徊…(20180325) [3]和歌の世界を徘徊…(20180325)
 [2]大人が蜘蛛で遊ぶ時代もあった…(20180210) [2]大人が蜘蛛で遊ぶ時代もあった…(20180210)
 [1]倭人にとって蜘蛛は吉兆…(20180205) [1]倭人にとって蜘蛛は吉兆…(20180205)
 蜘蛛を滅茶苦茶嫌った人々[続] …(20180220) 蜘蛛を滅茶苦茶嫌った人々[続] …(20180220)
 蜘蛛を滅茶苦茶嫌った人々 …(20180215) 蜘蛛を滅茶苦茶嫌った人々 …(20180215)
■■■ 日本の基底文化を考える ■■■
 「古今著聞集」の序とあとがきを読んで(20180902) 「古今著聞集」の序とあとがきを読んで(20180902)
 ボロこそが勿体ないの元祖では …(20160119) ボロこそが勿体ないの元祖では …(20160119)
 ラーメン食文化の見方…(20150827) ラーメン食文化の見方…(20150827)
 自殺文化国家…(20130912) 自殺文化国家…(20130912)
 国家観:似て非なるイタリア型…(20130626) 国家観:似て非なるイタリア型…(20130626)
 国家観では、アメリカ合衆国とは水と油…(20130624) 国家観では、アメリカ合衆国とは水と油…(20130624)
 車椅子利用者に対する姿勢について…(20130614) 車椅子利用者に対する姿勢について…(20130614)
 農耕民族論はそろそろ止めたら…(20130606) 農耕民族論はそろそろ止めたら…(20130606)
■■■ 言の葉遊び ■■■
 歌字倣-昆虫偏 …(20150329) 歌字倣-昆虫偏 …(20150329)
 孤島国根性…(20090806) 孤島国根性…(20090806)
 米信仰…(20090820) 米信仰…(20090820)
 温泉信仰…(20090903) 温泉信仰…(20090903)
 雑炊文化…(20090917) 雑炊文化…(20090917)
 米信仰[続]…(20090924) 米信仰[続]…(20090924)
 和食の不可思議さ…(20091001) 和食の不可思議さ…(20091001)
 唯一無二のハンコ社会…(20091008) 唯一無二のハンコ社会…(20091008)
 日本料理が抱える独特の食文化…(20091105) 日本料理が抱える独特の食文化…(20091105)
 方針なき時代区分の命名…(20100304) 方針なき時代区分の命名…(20100304)
 日本の横笛考[その1: 篠笛]…(20100316) 日本の横笛考[その1: 篠笛]…(20100316)
 日本の横笛考[その2: 龍笛]…(20100317) 日本の横笛考[その2: 龍笛]…(20100317)
 日本の横笛考[その3: 能管]…(20100318) 日本の横笛考[その3: 能管]…(20100318)
 日本の横笛考[その4: 7ッ指孔]…(20100324) 日本の横笛考[その4: 7ッ指孔]…(20100324)
 日本の横笛考[その5: 竹笛]…(20100331) 日本の横笛考[その5: 竹笛]…(20100331)
 日本の横笛考[その6: 錯綜する分類]…(20100401) 日本の横笛考[その6: 錯綜する分類]…(20100401)
 日本の横笛考[その7: 高麗笛]…(20100406) 日本の横笛考[その7: 高麗笛]…(20100406)
 日本の横笛考[その8: 大和笛]…(20100413) 日本の横笛考[その8: 大和笛]…(20100413)
 亀を称える体質…(20100618) 亀を称える体質…(20100618)
 日本人こそ、肉食民族で狩猟民族なのかも。…(20101029 日本人こそ、肉食民族で狩猟民族なのかも。…(20101029
 将棋に見る、日本文化の特異性…(20101202) 将棋に見る、日本文化の特異性…(20101202)
■■■ 日本語 ■■■ →「超日本語大研究」へ
 日本語は最古言語かも…(20090827) 日本語は最古言語かも…(20090827)
 日本語は最古言語かも[続]…(20090910) 日本語は最古言語かも[続]…(20090910)
 延々続く海外地名/人名の漢字表記…(20100222) 延々続く海外地名/人名の漢字表記…(20100222)
 日本語は雑種言語なのでは…(20101222) 日本語は雑種言語なのでは…(20101222)
 日本語だけは、 日本語だけは、
類縁性検討に特別な方法論が必要そう…(20110120)
 経典文字に抗してきた日本語…(20110121) 経典文字に抗してきた日本語…(20110121)
 トイレ表記に矢鱈こだわる人達だらけ…(20110210) トイレ表記に矢鱈こだわる人達だらけ…(20110210)
 日本の色彩感覚は全く違っていたのではないか…(20110216) 日本の色彩感覚は全く違っていたのではないか…(20110216)
 日本語の近しい近隣言語は存続危うし…(20110301) 日本語の近しい近隣言語は存続危うし…(20110301)
表紙>>>
(C) 1999-2018 RandDManagement.com | |